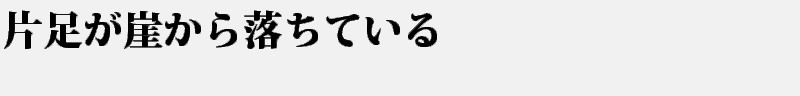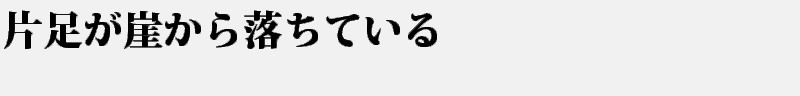|
男は寡黙だった。自らを無知と認め、いつも静かに口をつぐんでいた。その間も謙虚に知識を追い求め、書を捲る手は休むことがない。常に更なる一歩を踏み出そうと試みるその姿勢がルシフェルには大変好ましく思えた。
彼こそまさに無知の知だ。賢者と呼ばれるに足る精神を、あの男は持ち合わせている。
イーノックという人間が天界へ召し上げられてからというもの、大天使は非常に機嫌が良かった。当初は話が通じるペットを持ったような感覚でいたのだが、イーノックと接するうちにそんな考えは吹き飛んでしまった。彼は間違いなく個として存在すべき人間だ。互いに心を許すようになってからも畏敬の念を忘れぬ態度、自身の向上を目指す姿勢、自らを恥じるようなはにかみ顔、何もかもが好ましかった。天使と神のみを相手にしていた頃では考えられないほどの快感だった。
神の座へと続く大理石の名が廊下を裸足で踏みしめながら、ルシフェルはくすくすと思い出し笑いをした。
いやしかし、今日のは傑作だった。ジーンズを見せたときのあの反応といったら。太い両腕で贈り物を子どものようにこねくり回し、期待に目を爛々と輝かせるイーノック。着方を教えてやったら慌てて服を脱ぎ出した。
『ルシフェル、これでいいのか!』
でかい図体を跳ねさせながら満面の笑みで彼は言った。はは、無邪気無邪気。可愛いものじゃないか。
人間界の土産など、天使に見せたところで反応は高が知れている。彼らはそんなガラクタなんぞに興味はないのだ。鼻で笑われるか、小指で弾かれるのが関の山だろう。ならばあの男に渡した方が何倍も愉快というものだ。どうやら彼と私は好みが似ているようだしね。
さて次は何を持ち込もうか。あまり嵩張るものだと骨が折れるな、などと考えていたら、大天使は唐突に何かと衝突した。
ドン、と鈍い音。反動でよろめいてからハッと気付く。しまった、不注意だったな。見るとぶつかった相手は肩を押さえてうずくまっている。
ルシフェルは天衣から片腕を突き出し、助けを差し伸べてやることにした。
「すまない。大丈夫か?」
目の前の男はああ、ともええ、とも取れるような相槌を打つ。ローブに顔を隠しながら彼はルシフェルの高貴なる手を握った。
途端、じり、とひりつくような痛みが手の平を駆け抜ける。大天使は深く眉を寄せたが、握った手は離さなかった。離せなかったというべきかもしれない。あっという間に彼の白い手は火傷の後のように焼けただれる。ルシフェルは自らに起きた奇妙な変化を他人事のごとく一瞥した。
天使の身体は元より痛みに鈍い。しかし、これは一体どういうことだろうか。
ただれたルシフェルの手に気付くと、男は焦って手を離した。痛々しい見た目におどおどと慌てふためきながら、意味もなく辺りをきょろきょろと見渡している。その姿もまた滑稽だった。天使であれば一息で治癒できる程度の傷を前に、この男は成す術もない。余程低級の天使なのだろうか? 見れば彼の手にも同じような火傷の痕。
大天使はこの傷跡に見覚えがあった。そう、これはまるで地上の穢れに触れたときのような。
男は悲痛な声をあげた。
「ああ、これは、何ということだ」
「案ずるな。すぐ治る」
ルシフェルは唇を己のただれた手に押し当て、軽く赤い舌先をつけた。しゅう、と蒸気が立ち昇るような音がする。祝福の口付けを受けた右手は巻き戻しを起こしたようにみるみる治癒していく。やがて彼が唇を離すと、傷を負う前と何ら変わらない白い手が蘇っている。
荘厳な天使は伏せた眼を上げる。ぶつかった相手がどんな輩なのか一目見てやろうと思ったのだ。
そして視線は交差する。
「あ」
思わずルシフェルは声をあげた。意外にも男は見慣れた顔をしていた。
「サリエルじゃないか」
「……君か」
金の瞳をぎょろつかせ、大天使サリエルは呟いた。彼はルシフェルを認めると一変、三白眼をいぶかしむようにぐりぐりと動かす。人目を忍ぶようなその動きにルシフェルは小さく首を傾げた。
死を司る癒しの天使。水気の少ない金髪がローブの下から覗いている。照りつける太陽から逃れるような素振りの男は、間違いなくサリエルだった。高名なルシフェルにとっては数少ない同僚である。
馴染みのある相手にルシフェルは若干安堵した。
「驚いたな。誰かと思ったぞ」
サリエルは片頬を引き攣らせる。笑ったつもりらしい。
「すまない、少々考え事をしていたから」
「気が合うな。私もだよ。
それよりどうしたんだ。今日の君の身体には随分穢れが多いようだが」
さりげなくただれた右手を自らの体で隠しつつ、サリエルは服の裾を払う。砂埃が薄く宙を舞った。
「……俺は人の死を扱うからな。浄化が足りなかったようだ。
すまない、君にも傷を負わせてしまった」
ルシフェルはひらりと手を振る。この程度の傷、大したことではない。それにもう終わった話だ。それよりも未だ治癒されぬままで放置されている彼自身の火傷が気掛かりだった。もしかすると彼は仕事で治癒力を使い果たしているのかもしれない。それならば手を貸すことくらいできる。そう申し出てみるとサリエルは血の気の薄い顔をさっと白くして、困ったように肩を竦めた。
「気持ちは有り難いが遠慮しておこう。これは見た目よりも厄介な――そう――呪いのようなものだ」
サリエルの瞳が僅かに翳る。いつもと違う様子の彼をルシフェルは不思議に思ったが、あえて指摘することはなかった。
「そうか。差し出がましい真似をしたな」
癒しの天使である彼がそう言うのであれば、到底自分の手には負えないものなのだろう。それに、これ以上の詮索は無粋だな。見たところ、どうやら彼には何か触れられたくない事情があるらしい。ルシフェルは賢かった。だから彼は唇を引き結び、それ以上は何も突っ込まなかった。
この廊下を歩いてきたということは、サリエルは神にお目通りしてきた帰りなのだろう。煮詰まった話題を変えるためにルシフェルは前髪を掻き上げた。茶化したように笑ってみせる。
「呼び出しか? 優等生」
「少し、な。君の方こそ今日はどうしたんだ」
「私はイーノックに関する報告をしに行くんだ。
君も知っているだろう、あの人間の書記官だよ。神は心配性でね、お気に入りに虫がつかないか私に見張らせてるって訳さ」
「イーノック」
突然のサリエルの食いつきっぷりに、ルシフェルは思わず身を仰け反らせた。彼は濁った目をギラギラ輝かせながら更なる話題を求めている。イーノックに関する話題をサリエルの前でするのは初めてだったが、何がこれほど彼の興味を惹いたのか黒髪の大天使には分からなかった。
夢に浮かされたような口調でサリエルが言葉を紡ぐ。
「イーノック――ああ、あの人間の――そうだ、それはさぞかし素晴らしいだろうな」
そのときルシフェルが感じた感情を喩えるならば、それは『不快』の一言に尽きるだろう。何故そんな感情を抱いたのかと尋ねられても説明することは不可能だ。しかしそのときルシフェルは間違いなくサリエルの言葉を不快に思った。イーノックを見たことも、彼に会ったこともないこの天使に、彼の何が分かるというのだろうとまで思った。
ルシフェルは賢かったが、それと同等にサリエルも聡明だった。金の髪をふわつかせ、全てを見透かした彼が笑う。引き攣った笑顔でも無理をした笑顔でもなく、共感の喜びに満ちた表情だった。
「君は『彼』に執着しているんだな」
サリエルの発した言葉の真意が理解できず、赤目の天使は聞き返す。
「なんだって?」
「イーノックにだよ。君は彼が神のお気に入りだと言ったが、そうじゃない。
彼は君のお気に入りだ。違うのか?」
意味深な尋ね方だ。意図せず複雑な心地になる。そうだ、と言い切っても良かったのだが何故だか胸中がざわつく。結果としてルシフェルは横に首を傾げるだけに留めておいた。
一方サリエルは愉快そうだった。血色の悪い唇を薄く開いて、喉奥から密かな笑い声を溢す。目の前にいるサリエルは、本当に自分が知っているサリエルなのだろうか。ルシフェルは確信が持てなかった。癒しの大天使は前からこのような陰鬱な笑いを吐く男だっただろうか?
濁った瞳は黄金のようだ。三白眼を上目遣いにして、男は目尻を下げる。
「ルシフェル。君と俺は似ている」
「……褒められているのかどうか、私には区別がつかないよ」
「ただ事実を述べただけだ。君と俺は似ている。存在の根源が、特に」
ルシフェルは微笑むこともできずにいる。
鬱屈した天使はかかと笑って、立ち尽くす彼の横をするりと抜けた。別れの挨拶もなかったが、それが余計に不気味さを醸し出した。何だあの男は、とルシフェルは心から混乱を覚えた。あの男はサリエルだったのだろうか。背筋を駆け上がる冷たい違和感。
彼は赤い視線を遠のくサリエルの後ろ姿へ投げた。ぶらぶらと揺れる手は未だに焼けただれたままだった。
僅かな回想の後、ルシフェルは再び廊下を歩く。ひやりとした床が指先を冷やした。思いがけず時間を食ったが、やるべきことは多い。神に書記官の仕事振りを報告しなければならないのだ。今頃は焦れて足を踏み鳴らしている頃だろう。急がねば、また小言で時間を食われることになる。大天使も楽じゃないのだ。
厳粛な長廊下を最奥まで進むと、壮大な金の扉がそびえ立っている。細やかな装飾が施された取っ手を掴んで押し開ける。
台座に神が足を組んで腰を下ろしていた。
「遅いぞ、ルシフェル」
「すまない。立ち話に興じていてね」
何食わぬ顔で書類を手渡すと神はつまらなさそうな表情を隠しもせずにぱらぱらとページを繰った。イーノックの様子を知りたいと言うから定期的に運んできているというのに随分な態度だ。驚異的なスピードで最終頁までを読み終えると、神は書類を台座の横へ投げ捨てた。
「ともあれ、よくこなしているようじゃないか」
「恐らく君の期待以上だろうさ。実際あいつはよくやっているよ」
補足的に付け加えた言葉は何故か神の琴線に触れたらしい。退屈そうな眼差しを上げ、神はルシフェルを一瞥した。きょとんと呆ける大天使を前に神は溜め息をつく。深い、諦観の籠もった溜め息だ。
異様な様子にルシフェルが眉間に皺を寄せる。誰も彼も、今日は一体どうしてしまったというんだ。
「どうした。随分感傷的じゃないか」
神は少しだけ言い淀み、続ける。
「サリエルに会っただろう」
「ああ。さっきもそこで立ち話をしてきたところだ」
「あれはもうじき堕天するだろう」
雷に打たれたような衝撃が全身に走る。耳に入った言葉を噛み砕くことができず、ぽかんと大天使は口を開けた。
堕天? サリエルが? あの人格者である大天使に限って、まさか。
ぐるぐると混沌の渦に回る頭の中、先程見たサリエルの濁った二つの瞳がフラッシュバックする。握った手は互いに焼けただれた。まるで穢れに触れたようだ、とルシフェルは思った。彼はその穢れを死に関わったせいだと言ったが、何故彼はルシフェルに触れるまで火傷を負わなかったのだろうか。穢れに触れた時点で焼けただれていても良いはずだ。だが、穢れは彼の身体に馴染んでいた。
だとすれば、それこそが彼自身が穢れている証拠ではないのか。
「サリエルはお前の神気にやられたんだろう。穢れは神気に弱いからな」
「……にわかには信じがたい話だな」
どよめく胸中を抑え込みつつ、ルシフェルは飄々と言い放った。頭の芯が冷えていく感覚。そのうちルシフェルは新たな疑問がむくむくと首をもたげてくるのを感じていた。
『君と俺は似ている』
果たしてあの言葉はどういう意味だったのだろう。
堕天する気など心にもない。天界での暮らしに不自由はなく、自らの立場に文句もない。大天使としての誇りもある。何より、今はイーノックという人間を眺めているだけで満足だ。つまらない反旗など翻すつもりも起きないね。
そうだ。サリエルは友人ではあるが、まったくの他人事に過ぎない。
腕を組むルシフェルを一瞥し、神は目を細めた。冷たい視線が胸を刺すので大天使は口角を下げる。そのような視線を受ける筋合いはない。
「君まで何だ。どうしてそんな目で私を見る」
「いいや」
神は小さく肩を竦めた。漂うのは冷え切った諦め。
「口にするのも馬鹿馬鹿しい話だ。だが、一応忠告しておくか」
「何を」
「黙って聞け。いいかい」
苛立ち気味の天使の話に有無を言わせず割り込んで、神は足を組み替えた。視線は無知なる存在を憐れむような色を帯びている。
「足元には気をつけなさい、金星の守護者よ。まあ今更遅いかもしれないが」
言われるがままに、ルシフェルは自らの足元をじっと見つめた。両の足はしっかりと天界の床を踏みしめ、微塵も危うくは見えなかった。まさかその片足が崖から落ちている訳もなく、だから飄逸な大天使は自らに沸き起こった不安を鼻で笑い飛ばすのだった。
▲戻る
|