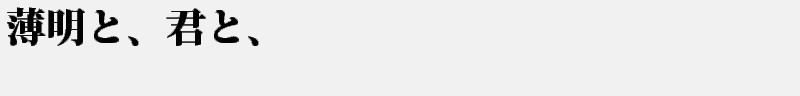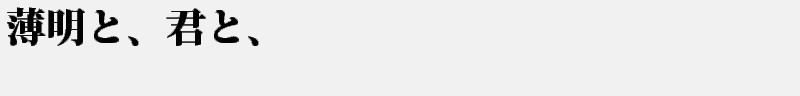|
深夜の散歩は数少ない趣味のひとつだった。澄んだ空気を肺に取り込みながら――といっても、天使は本来呼吸など必要無いのだが――歩いていると、脳の芯がピンと張り詰めるような感覚があった。白い息を吐き出し、ルシフェルは真っ黒な空を見上げる。
月もない夜だ。一際強い光を放っているのは金星だろうか。
真っ暗な夜が好きだった。大空を翼で駆けるよりも、自らの足で歩く方が好きだった。天使仲間には敬遠され、陰で小馬鹿にする者もいた。ルシフェル様のあの言動はなんだ。まるで人間の真似事じゃないか、と。
ルシフェルは一向に気にしなかった。どうせ闇が隠してくれるのだ。
一陣の風が吹く。体温が奪われるのを感じて、彼はシャツの前を掛け合わせた。
「さすがに冷えるな……」
触れてみると、首筋が氷のようだ。そろそろ戻らねば。眠っているイーノックが目覚めた際、傍らに誰もいなければさぞ心細かろう。
うんと伸びをする。肩甲骨が薄い皮膚を突き破り、六枚の白い翼が大きく広がった。帰りは飛んだ方が断然速い。それに、あてもなく歩いてきたせいで帰路が分からないというのも本音だった。
爪先で地面を蹴る。黒い海に身を投げるように、頭から夜空へと飛び込んだ。星々を誘導灯にしながら、ルシフェルは暗闇を駆けて行く。
聖なる力で護られた寝床へと降り立つと、彼はそっと天蓋をめくった。眠りこけているだろう男の顔を一目拝んでやろうと思ったのだ。
しかし予想外なことに、めくった先には誰もいなかった。
「イーノック?」
囁くように声を掛けてみる。だが、返事はない。見ればランプの灯りもすっかり消えている。
嫌な予感がして、ルシフェルは中へと駆け込んだ。白い吐息が肺から押し出される。慌てて麻で編まれた敷物を触っても、体温すら残されてはいなかった。
野党にでも襲われたのだろうか。いや、もしかするともっと邪悪なものに? そんなはずはない。神気の護りは鉄壁で、他の存在からは目に見えもしないのだ。護りを破られるとはすなわち神が破られるのと同意義。侵入者など有り得ない。
それでは、一体?
辺りに暗雲がじわじわと滲み出す。嫌な暗さだ。手探りでランプを掴み、なんとか火を灯す。ぼうっと天蓋内が明るくなっても、イーノックの姿は見当たらなかった。落胆の溜め息が漏れる。
そこで俯いた瞳に、オレンジ色に照らされたある物が飛び込んできた。枕元へ無造作に置かれたそれは、
「手紙……?」
羊皮紙には見慣れた文字が流れるように綴られている。角が丸まっているそれを摘まみ上げ、そっと広げてみる。間違いなくイーノックの字であることに安堵しながら、ルシフェルは早速冒頭から目を通し始めた。
肝心の内容はと言えば、このようなものだった。
『親愛なるルシフェル
夜明けまでにこの手紙が君に読まれることを願いながら、これをしたためている。本当は直接声を掛けたかったんだが、目覚めたときには既に君はいなかったから。君は常に薄着だから、風邪を引かないか心配だ。
もし君がこれを読むとき、まだ宵の明星が何よりも明るく輝いていたとしたら、近くの山岸まで来てくれ。君の翼に追い抜かれない限りは、私は先にそこで待っている。我が儘を言ってすまないが、君に来て欲しいんだ。子どもの頼みとでも思ってくれ。
くれぐれも、暖かい格好で。
君の友人 イーノック』
はは、とルシフェルが笑った。油断しきった笑いだった。
「嘘をつくなよ、イーノックめ」
羊皮紙を大事に折り畳み、ジーンズの尻ポケットへぐいと突っ込む。
「友人とは口付けなどしないだろうに」
火を灯したばかりのランプを手に取り、ふうと息を吹き掛ける。火は消え、再び暖かな闇が戻ってくる。柔らかな黒を味方につけながら、ルシフェルは静かに天蓋をめくった。外は未だ夜明けも遠く、金星は変わらず瞬いている。
さて、珍しく我が儘な子どもを迎えに行ってやろう。大天使は翼を広げる。何が目的かは知らないが、イーノックが呼んでいるのだ。向かう理由などそれだけでいい。あれのお守が自分に課せられた指令であり、同時に本望なのだから。
天使の体が重力もなく、すい、と浮かび上がる。雪のようにふらふら舞いながら、ルシフェルの姿はあっという間に闇夜へと消えて行った。
イーノックはかじかむ指先を擦り合わせていた。赤く腫れ上がった手はほとんど感覚もない。くれぐれも暖かく、などと書いておきながらこの有様だ。情けない。
白霧のような息を吐き出しながら、彼は頭上に広がる空を見上げた。青い瞳に深い黒が映り込む。底のない闇だ。永遠を感じさせる途方もない深さに、身震いをひとつ。果てがないとは何と恐ろしいことだろう。
それでも、視界の端に金星を見つけるだけで、ほら。これほど落ち着いた心地になる。
「金星の守護者――」
赤みがかった光は彼の瞳を思わせた。薄く微笑んで、イーノックは擦り合わせていた手を緩く下ろした。
と、突然ブラックアウトする視界。奪われる視覚情報。
ぎょっとしてイーノックは仰け反った。どうやら両目を塞がれているようだった。しかしそれに気付いてしまえば、もはや怖がる必要はない。純朴な青年は思わず笑い出して、自らの目を覆う手を重ねるようにして掴んだ。愛しい名前を呼びながら。
「遅いぞ、ルシフェル」
「指定する場所が悪いんだ」
宵の明星よりも明るい双眼が男を見つめている。ルシフェルは切れ長の瞳を細め、どっかりと隣へ腰を下ろした。
「さあ、言われた通りに来たぞ。今日はどんな風の吹き回しだ?」
イーノックは意味深な様子で小首を傾げて、腰掛けた断崖の向こうへと視線を投げた。どこまでも平らな海が広がっている。黒い空と黒い海に境目はなく、薄っすらと照り返しの線が引かれているだけだ。大天使は訝しげに青年を観察して、それから仕方なしに自らも海を眺めた。ざざあ、ざざあ、と波の音がする。
やけに静かな気持ちになる。陶器の花瓶にでもなった気分だ。
「今日は特別な日だそうだ」
イーノックがこっそり口を開く。
「特別な日?」
「ナンナに聞いたんだ。今日は、年の終わりだったらしい」
「年の終わり」
聴き慣れぬ単語を舌で転がしながら、ルシフェルが尋ね返す。
「そうだ。そして陽が昇ると、そこから新しい年が来る」
「妙な観念だな」
ルシフェルは人間の持つ時間感覚に思わず頭を捻った。時間を自由に飛び回ることのできる大天使にとって、時の流れに新旧はなかった。ましてや年などという区切りもない。だが目の前のイーノックがやけに嬉しそうだったので、野暮なことを口にするつもりはなかった。
イーノックは少しだけはにかむと、おそるおそる手を差し出す。青い瞳が星のように輝いている。
「手を、繋いでくれないか」
「……積極的だな」
「年の瀬とは感傷的になるものらしい」
「そんなものか」
黒髪の大天使はもどかしく湧き上がる気持ちを抑えながら、硝子でも掴むようにイーノックの手を取った。白と褐色が絡み合い、ぐっと結ばれる。不慣れな行為に二人は顔を見合せながら、不器用に笑顔を突き合わせた。
天使の手は冷たく、人間の手もまた同じだった。互いの冷たさを互いに受け入れ合いながら、二人はどちらからともなく寄り添う。肩がそろそろと近付く。遂にぶつかると、電流でも流れたかのように二つの影が動きを止めた。
「新しい年になると、何が起こるんだ」
ルシフェルが目を合わせずに問い掛ける。
「分からない。ナンナも教えてくれなかった」
「それなら、確かめないとな」
賑やかな天使は口数を減らし、それからは何も言わなかった。無骨な指を指でなぞりながら、繋がった空と海を見つめている。イーノックは喉をぐっと締める。美しい大天使からは光のような香りがした。触れ合った部分が熱を帯びていく。
四本の足をぶらつかせながら、二人の男の背中が並んでいる。じっと息を潜め、起こるかもしれない何かを待ち望んでいる。その光景はさながら一枚の絵画のようで、しかしそれを目にする者は誰もいなかった。世界はどこまでも二人きりで、金星だけが寄り添う人影を照らしている。
海と空との境目から薄明が訪れたとき、彼は何を思うだろうか。
一昨日と昨日、昨日と今日が何ら変わらぬことは知っている。それでも二人は薄明を望んだ。その薄明が願わくば相手に奇跡を起こさんことを、と念じながら、二人は固く互いの手を握り合ったのだった。
やがて、一筋の光が空と海を分ける。
明けましておめでとうございます!
今年も一年、『ビニール傘と無鉄砲』をよろしくお願いいたします。
2011.01.01 タマミヤ
▲戻る
|