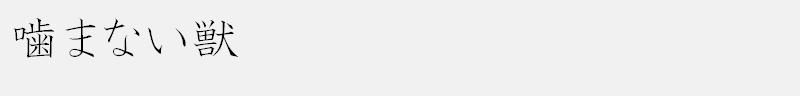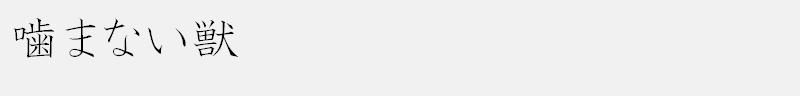|
古ぼけた羊皮紙にはインクの跡が滲んでいる。重ねた年月を思わせるような擦り切れ方だ。男は武骨な指でそれを摘まみ上げると、表面の埃をふうと吹き飛ばした。あるものは端が脆くも欠け、あるものは湿気に晒されてすっかり読めなくなっている。
男は愛おしげにそれら一つ一つを眺めながら、静かに目を細めた。睫毛の間からは少し哀しげな両の瞳が覗いている。哀愁の漂う背中は先ほどよりも縮こまってしまったかのように、格好悪く丸まっている。古樹の枯れ木のようなどっしりとした体躯が、柳のようにうなだれている。だが、それを誰が見咎めるというのだろう。誰が彼を叱責するというのだろう?
羊皮紙に走るたどたどしい筆跡を、男は人差し指でつうとなぞった。膠(にかわ)はすっかり乾き切っていて、後から後から剥がれ落ちてしまう。
ああ、と彼は深い溜め息を吐いた。
剥がれたインクがぱらぱらと足元へ散っていく。黒い粉雪のようにも見えた。裸足の足を汚しながら、それでも男はなぞる手を止めなかった。インクの欠片は次々と剥がれ、そよ風に奪われていく。
頬を撫ぜる空気の流れと共に、あの日の記憶が呼び起こされる。羊皮紙は見る見るうちに瑞々しさを取り戻して――
彼はインク壷に筆先をつけようと手を伸ばしたところで、その中身が空であったことに気付いた。かつん、と硬い音がする。ペン先が底のガラスに当たったのだ。
羽ペンがインクを吸い上げなかったことを確認し、イーノックは軽い溜め息をついた。乾いた先端で羊皮紙をなぞっても、新たな筆跡は描かれない。そこでようやく彼は数刻振りに筆を置き、指を組んでうんと伸ばした。
「呆れた集中力だな」
唐突に声を掛けられ、彼は僅かに肩を揺らした。呼び声の主は斜め前にのんたりと頬杖をついていた。相手の姿を認めた途端、鼻腔にほんのりとユーカリの香りが漂ってくる。生い茂る草木の中に鼻先を突っ込んだときのような爽やかさだ。
新たな酸素を肺いっぱいに取り込んだような心地になって、イーノックは目を細める。そして再び目を開けたときには、彼の身体から緊張はすっかり解けていた。
「驚かせないでくれ」
「随分前から居たには居たよ。君が気付かなかっただけでね」
ルシフェルという名の大天使は優雅に上着のポケットへ手を突っ込む。白い指は中から新たなインク壷を取り出し、机の上にそれを置いてやった。
「ほら、使え」
ありがとう、と言いながらイーノックがガラス壷に手を伸ばす。しかし爪が触れようとした瞬間、ルシフェルがひょいとインク壷を引き寄せた。青年の手が空を切る。きょとんと目を瞬く彼を見ながら、天使はさも愉快そうに笑った。悪戯が成功したときの子どものような顔だ。
もう一度手を伸ばす。が、インク壷はすいと逃げてしまう。
さすがに少々眉を寄せて、書記官は抗議の声を出した。
「ルシフェル」
「少しは休め。
ペンだこから血が出てるじゃないか。それ以上指を太くしてどうする。そのうちペンもへし折れるぞ」
イーノックは言われて初めて気付いたようだった。薄汚れた指の第一関節に視線をやると、恥ずかしげに服へ擦り付ける。黒いインクの筋が絹のローブに線を描いた。乾いた血の跡がその上をなぞる。
大天使はガラス瓶の蓋を回し開けた。真新しい、墨独特の匂いが部屋に充満していく。ルシフェルは鼻を揺らして柔らかい微笑を浮かべた。
「それに、水臭いじゃないか。こんな楽しそうなことに私を呼ばないなんて」
置かれた羽根ペンを取り上げると、インク壷の中へ。樫の木でできた柄に墨が撥ねる。
ルシフェルはイーノックの手元から書きかけの羊皮紙を摘まみ上げる。お世辞にも美しいとは言えない文字が並んでいる。なんとか読めなくもないが、書記官の任を負っているにしてはあまりにもお粗末だ。失笑にも似た、それでいて親鳥の温かさにも似た笑みが天使の唇を掠める。
イーノックが書いていたのは、いわゆる『天界語』と呼ばれる文字だ。
とはいえ、そう呼ぶように決めたのは彼自身である。イーノックがかつて下界で使っていた文字と区別するため、便宜上そのように呼んでいる。ちなみに、彼が召し上げられるまでそれらの文字に名前はなかった。
天界語は彼が書記官としてこの地に招かれた際、とりわけ感銘を受けたもののひとつだ。流れるような筆跡の美しさ。絵画のように完成された芸術。天界語で書かれた一文を目にしただけで鳥肌が立ち、気高さに胸が詰まる。当初は書記官としてその文字を扱えるという喜びに打ち震えたものだ。
しかし、いざ彼が練習し始めてみると、すぐに頭を抱えてしまうこととなった。上達の歩みが著しく遅いのだ。それには幾つかの理由がある。
まず、天界語自体の言語体系が極めて難解であること。
そもそもの天界語は、いうなれば音楽のようなものであるらしい。書きとめた天界文字は、いわば天界語を演奏するための楽譜と考えるのがいいだろう。だが、それらの楽譜は流れるような筆跡の美しさによって表される。川のせせらぎのように、あるいは風のざわめきのように、響きのまま文字をおこさねばならない。文法や文字の形状にも明確なルールが存在している訳ではなさそうなのだ。
下界で生まれ育ったイーノックには、下界の感性しか備わっていない。天上人の奏でる音を聴き、文字という楽譜におこすことなど、並大抵の努力ではこなせない。
更に、書記官という職務上、執筆にはスピードも要求される。一文字を描くのでさえやっとなのだから、エルダー評議会で繰り広げられる激論へは到底ついていけるはずもない。結果として執筆には予定以上の日数が掛かってしまい、イーノックのスケジュールを圧迫する。
勤勉な青年にとって天界語の習得は、他の何を差し置いてでも達成すべき事柄だった。一刻でも早く、それでいて非の打ち所のないように。
「君の書く字は、こう、硬いな」
書記官の不器用な筆跡をなぞりつつ、ルシフェルが首を傾げる。
イーノックはしょんぼりと頭を下げながら肩を縮こまらせた。
「神は何故私に書記を任されたのだろうか」
「全ての意図は酌めないが、君に才能を見出したからだろうさ」
「私に才能があるとは思えないが……」
「いや、感性はいいよ。センスはある。だが、圧倒的に経験が足りないな」
ううむ、とルシフェルが唸る。そして、天使の指がインク壷の中の羽根ペンへ伸びた。
彼はイーノックが書いた文字列の下に、同じ内容の文章をさらさらと書きつけ始める。全ての文字が流れるように繋がり、美しい旋律の模様を描き出す。羊皮紙自身が今にも歌い出しそうだ。
「だが、見ろ、並べればそう変わりはしな……」
大天使が顔を上げると、イーノックが冷ややかな目で自らの文字を見つめていた。
「……すまない。言い過ぎたな」
実際、並べてみるとその差は一目瞭然だ。未熟な書記官の文字は処理の甘い金属のように硬く、ささくれ立っている。かたやルシフェルの記した文字は海のようにたゆたい、小刻みにさざめいている。イーノックは疲労困憊といった様子で、がっくりと肩を落とした。
どうにかしてやりたい、と大天使が思う。彼の血の滲むような努力は見てきたつもりだ。しかし、感性だけは一朝一夕で身につくものではない。見たところ、この習得ペースではあと十年は掛かりそうだ。それまでにイーノックが激務で身体を壊しては元も子もない。友人として、それから共にいる者として、どうにか助け舟を出してやれないものか。
感性は決して悪くない。荒削りだが、センスも感じる。だが圧倒的に経験が足りない。天界語を自在に操るという経験が。
音の響きを耳へ染み込ませ、文字の流れに身体を慣らさなければ……。
大天使ルシフェルは非常に聡明で、その上閃きに優れていた。
彼は突如降ってきた自らの思いつきに、思わず赤い唇を吊り上げた。
なんだ、あるじゃないか。私たちの言葉を彼に染み込ませ、ペン先を流れのままに走らせる方法が。ああ、なんと素晴らしい思いつきだろう!
賢明な天使ルシフェルは細い足をすいと踏み出して、うなだれるイーノックの背後へ歩み寄った。後ろからぽんと肩を叩き、そのまま手を二の腕まで滑らせる。
「なあイーノック、いいことを思いついたんだ」
触れられた手から不穏な空気を感じ、青年はおそるおそる顔を上げる。間近で見るルシフェルの瞳は、自らの名案に爛々と輝いていた。これにはさすがのイーノックも僅かに仰け反る。しかし、置かれた手は二の腕に位置したままだ。
「いいこと?」
「そうだ。君が我々の言語を解するための手助けを、ね」
陶器のような頬が笑みを模す。先程よりも強いユーカリの香りがして、書記官は心臓がどうかしてしまいそうだった。ただでさえこれほど近くにルシフェルの顔があるというのに、腕に置かれた手はじりじりと手首まで迫り始めている。
てだすけ、と、浮かされたような声でイーノックが繰り返す。ルシフェルの指がイーノックの手に重なり、包み込むように握られる。
マリオネットでも動かすかのように、天使は彼の手を持ち上げた。操られた手は一直線に伸びていき、再び羽根ペンを青年に掴ませる。そのままペン先を羊皮紙へ持ってこさせた。インクが玉となって落ち、血の跡のようなものがぽたりと描かれる。
ルシフェルは舌なめずりをした。血色の良い唇が、そうっとイーノックの耳元へ近づく。
そして、彼はとびきりの声で囁いた。
「“さあいい子だ、イーノック”」
低い、謳うような、どこまでも甘い声。
耳朶にルシフェルの声を受けた途端、イーノックの身体が痺れるように跳ねた。まごうことなき天界語だ。世界中の愛の賛美を一身に受けたかのような衝撃が彼の身体を渦巻いていく。青年はぱくぱくと口を動かして、紡げない言葉を必死に紡ごうとする。
ふふ、とルシフェルは笑った。そのまま彼の手ごと指先を動かし、羊皮紙にあの美しい文字を描いていく。
『さあいい子だ、イーノック』、と。
陽に焼けた書記官の顔が、徐々に朱色を帯びていく。
「“楽しいお勉強の時間だよ”」
悪戯な天使が囁くと、イーノックの手もその通りに言葉を描く。
「“考えずに、感じるんだ。私の指と、声と、君の感覚を”」
青年は自分の手が、今までに感じたことのない、何か素晴らしいものを描き出していることを感じた。自分を背後から抱くルシフェルの身体と、されるがままになっている自分の身体と、部屋に流れる空気とが渾然一体となったことを感じた。世界の中にたゆたうように、自らが音楽にでもなったかのような感覚。
「“いいぞ。それなら、手始めに愛の言葉の練習でもしてみようか。勉強は興味のある分野からがいい”」
ルシフェルが笑うと、熱い吐息がイーノックの耳朶を甘く刺激する。天使はゆるゆると顔を近付け、距離を詰め――
「“私が訳してあげるから、言ってごらん。君の知り得るだけの愛の言葉をね”」
回想が途切れ、イーノック――もといメタトロンは、ようやく文字から目を離すことができた。古ぼけた羊皮紙からゆっくりと顔を上げる。
深い悲しみに満ちた蒼色が彼の瞳をたゆたっていた。寄せては返す波のように、彼の視点がぶれる。
今にも割れそうな羊皮紙の上には、あの頃抱いていた青い愛がありありと示されていた。インクが掠れ、表面が剥がれ落ちていく。それほどの過去であるはずなのに、今でも鮮明に思い出すことができる。そして思い出すたびにこうして胸が詰まるのだ。自分の想いと、ルシフェルの想いとを思うたび、メタトロンは泣きたくて仕方がなくなる。
けれど、涙はいつまで経っても出ない。涙は蒼色に形を変えて、新たに瞳をたゆたうだけだ。もしかすると彼の赤い瞳も、何かの感情だったのだろうか? 今となっては確かめる術もない。
ああ、と彼は深い溜め息を吐いた。
それから彼の名前を小さく呟き、続けて流暢な天界語で囁いたのは、皮肉にもあの頃学んだ愛の言葉だった。
▲戻る
|