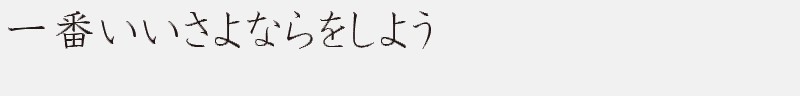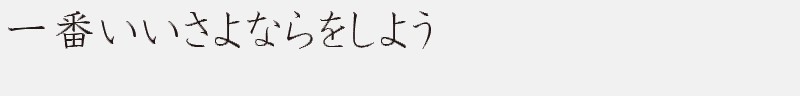|
視界を失う不安といったら途方もない。よろよろと導かれながら、彼は少女ナンナの苦労を改めて思った。イーノックの信仰は盲目的ではあったが、実際瞳を潰したことはなかった。光を失いながらも歩み続けた彼女のなんと健気だったことか。
かたや自分はこうして誰かに導かれなければ、一歩とて安心して踏み出すことができない。
「あまり強く掴むな」
ぶっきらぼうに言いながら、ルシフェルは部屋の中へと進む。
光の満ちた空間には天井も壁もない。果てがないのか、それともあるのか、それすら誰にも分からなかった。視覚を遮った分、書記官の感覚は鋭く研ぎ澄まされていく。地を踏み締める足は柔らかく受け止められ、まるで雲の上を歩いているようだった。
では鼻腔をくすぐるこの匂いはなんだろう?
太陽と炎の香りだ、と彼は思い当たった。
『お帰り』
突如響いた声に、思わずイーノックは膝を折った。
その際ルシフェルの腕を掴んだままだったので、はからずも彼までよろめいてしまう。
「おい、イーノック」
不服そうに天使は言ったのだが、イーノックは膝を折ったままでいた。
声には聴いた人々を無条件に平伏させてしまう圧倒的な響きがあった。あまりの畏怖に青年は仔羊のごとくがたがたと震え始めた。
全ての父、全知全能の我が主が、今自分の目の前におられるというのだろうか。
そう考えると、どう頑張ろうとも彼は再び立ち上がれる気がしなかった。
ルシフェルは自分の腕に縋りつく手を見た。こもる力のあまり、爪が白く変色している。大天使は仕方なしに溜め息をついた。
「まったく」
肩をすくめて彼は台座を睨む。それ見たことか、とでも言いたげな眼差しだ。
「君のせいだぞ。見ろ、怯えているじゃないか」
忍び笑いが部屋に満ちる。そよ風と共に炎の匂いが一層強まった。
『立ちなさい、イーノック』
すると途端、まるで糸にでも吊られたかのように、青年の両足は硬直から自由になった。おそるおそる彼は自らの膝へ触れてみる。震えは止まっていた。それどころかどこかじんわりと温かい。誰かに撫でさすられたかのようだった。
『ご苦労だったね、ルシフェル』
「疲れたよ」
何の躊躇いもなく天使は言う。
『そしてイーノック、見事な働きだった』
声も出さずに書記官は尚深く頭を垂れた。もはや額が床にくちづけしかねない勢いだ。
そんな青年の愚直な態度に、大いなる存在はまた笑い出す。慈愛に満ちた笑いだ。
声は豪胆な男のように力強く、また、淑やかな乙女のようにたおやかでもあった。瑞々しくもあり、老成し切っているようでもある。だから無数の声が混ざり合っているのかと思って聞けば、やはり声はひとつなのだった。
主の御姿を一目見たい、とイーノックは思った。しかしすぐに浅ましい考えを打ち消す。彼は敬虔で慎ましかったのだ。
震えは治まったが、未だイーノックは膝を折ったままでいる。
呆れた天使は彼を放り出してふわふわ歩き出した。そうして光る台座の傍へ行き、パチンと指を鳴らす。たちまち白い牛革のソファーが現れた。
『久々だというのに、まるで自分の家のような振る舞いだな』
神の声が漂う。面白がっているようだった。
「君の膝元が私の家だよ」
さも当然といった風でルシフェルが腰を下ろす。革製のソファーは上質で、彼の細い身体をゆったりと抱きとめた。柔らかな背もたれに身を沈めながら穏やかに息を吐く。
ルシフェルはうつらうつらと目を細めた。
「イーノックに話があるそうじゃないか。あいつ、放っておくといつまでもああしているぞ。
あいつを大理石像にでも仕立てて、この部屋のインテリアにでもするつもりかな。幸いこの広さだ、置き場には困らないだろうが」
『お前は変わらずよく喋る』
神は光るその御手をかざした。
するとルシフェルのソファーはするすると動き始める。生命を宿したかのような動きに、大天使は怪訝そうに彼を仰いだ。
「何のつもりだい」
『暫くイーノックと二人にしておくれ』
大天使は不満を顔いっぱいに表した。
「来て早々この扱いはないんじゃないか。私は邪魔者というわけか」
むすっと唇を尖らせる。
大天使を乗せたまま、ソファーは滑るように部屋の奥へ。
『後で呼び戻すとも。さあ、いい子だから大人しく待っておいで』
「君こそ変わらず調子がいいことだ」
最後に皮肉を吐いてみせ、ルシフェルの姿は見えなくなった。
部屋には目を固く閉じたイーノックのみが残される。だだっ広い空間にぽつりと座る彼は、もはや身の細る思いだった。
巨大な台座の上で、光の塊がそっと足を組み替えた。
『さて、さて』
満足そうに言う声を、青年は顔も上げずに聞いている。
『お前が無事《結末》へ辿りつけたようで何よりだよ。満足のいく選択はできたかい』
「……分かりません」
口を開いてまず出たのは歯切れの悪い言葉だった。
無意識のうちに出たうやむやな返答に自分でも驚きながら、イーノックははっと口をつぐむ。ぽろりと落ちた本音の存在は大きかった。
神は、ふうむ、と意味深な声色で唸ってみせる。
『続けなさい』
書記官は困惑した。
そうして深い躊躇いの後、恐れながら、と言葉を紡ぐ。
「確かに堕天使は姿を消しました。
ですが、それだけです。人間たちは弱いままだ。
――神よ。地上はこの先、平和を保つことができるのでしょうか。我々はこれからも常に良い選択を取り続け、悪なるものを退けることができるのでしょうか」
『お前は賢いね』
彼は素直に感心したようだった。
だがその響きを聞くと、何故かイーノックの心には不穏な影が落ちた。主の言葉に何か予言めいたものを感じたからだ。つい表情が強張る。
もし、今感じているこの不安が本物だとしたら。
「神よ、どうかお答え下さい。この先の未来において、洪水が地上を押し流すことは決してないのだと仰って下さい。ただ一言でいいのです。それだけで私は救われます」
神は答えなかった。
何も言わずにいることで、それを答えの代わりとした。
イーノックは打ちのめされた。
洪水はやはり訪れるのだ。
遠い未来かもしれない、近い将来かもしれない。けれど確実に洪水は訪れて、故郷のあの地を押し流してしまうのだ。
彼は奮える己の手をかき合わせた。握り合った両手がぶるぶると青ざめる。この手はなんと無力なのだ。血を吐くような声で青年は叫んだ。
「我らが主よ。我々人間はただ、滅びに向かって進むしか道がないのでしょうか」
即答はない。奇妙な沈黙だけが場に流れていく。
『そうとも言えるし、違うとも言える』
不思議とぼんやりした声で彼は言った。
『暗い夜道を好んで歩む者もいれば、夜道を照らす光となる者もいるのだ。光も届かぬほど夜が暗くなれば、光さえ闇に飲まれることもあるだろう』
神の言葉はまるで絞首刑を宣告する裁判官のように響いた。イーノックは死刑囚に似た顔をして、その声を厳かに聞いていた。
頭をよぎるのは旅での思い出だ。旅の最中に出会った人々の顔が走馬灯のごとく浮かんでは消える。
村で出会ったうら若き娘、自分をエヴェドと呼んだ親しき戦友、自由の民の長シン、そしてイシュタールの魂を宿した少女ナンナ……。
思い返してみれば、光自体は多くあったのだ。しかしそれにも関わらず、地上は暗く覆われていた。微かなそれぞれの光だけでは打開できないほどに沈み切っていたからだ。あのときイーノックという決定打がなければ、確実に下界は闇に溶けたまま戻らなかっただろう。
だがこの先、再び地上に危機が訪れたとして、それを誰が救うというのだろう。そのときに応じて選ばれるのだろうか、それとも『二度はない』と見放されてしまうのだろうか……。
青年には分からなかった。普通より遥かに長い生を受けているとはいえ、未だ分からぬことは多い。
ただひとつだけ分かることがある。自らの中で沸き起こる正義感が、このままではいけない、と警鐘を鳴らしているのだ。
「主よ、私にはもう何もできないのでしょうか」
咄嗟にイーノックはそう口に出していた。長旅から戻ったばかりの男の言葉とは思えないほど力強かった。彼の声には覇気があり、何よりも決意が滲んでいる。使命感に胸を熱くたぎらせながら、彼はぐっと拳を握った。
固い手のひらへ爪が食い込む。
「彼らが最良の選択を取る為に、私ができることはないのでしょうか」
ふわり、と何か温かい塊が頭へと触れる。書記官の金の髪が緩やかに揺れた。
感触自体は微々たるものだったが、喩えようのない安堵が胸をいっぱいに満たしていく。
神に撫ぜられているのだ、とイーノックは思った。
主の右手が今、私の頭に触れている。
『お前は本当に聡い子だ』
憐れみに満ちた声で彼は囁いた。
『実のところ、お前がそう言い出すことは分かっていたとも。そしてこの先には、お前の選択によって成り立つ未来がある』
「私は何をすれば良いのでしょう」
瞼を下ろしたままイーノックは尋ねた。
「何も持たぬ身の上ですが、全てを捧げましょう。それで彼らが救われるのなら」
『イーノック、もう一度地上へ降りておくれ』
粛然と神は言う。閉じた瞼の裏が一層白んじた。聖なる光の下に青年は全てを露呈させられる。これ以上目を閉じることも叶わず、もはや光から逃れる術などないのだった。
『そうして地上で善なる乙女を見出し、その娘との間に子を成しなさい。
お前のもとには男の子が生まれるだろう。その子をメトセラを名付けるのだ。お前はそこでようやく、使命を帯びた長い生から解き放たれるだろう』
神のお告げは粛々と響いた。
イーノックの頭上には祝福の光がこの上ないほどに注がれた。幾種もの花の香りが漂い、同時に花びらの雨が彼に向かって舞い落ちた。全知全能の主は彼に進むべき道を示し、人間たちへ再び救いの手を差し伸べたのだった。
だが、イーノックには返事ができなかった。
声を出そうにも音が出ないのだ。彼は言葉を喉に詰まらせて、今にも窒息しかねなかった。
はい。御心のままに。
その一言を紡ごうとして青年は必死にもがいていた。
何故御心に従うと即答できないのだ。全てを捧げると誓ったではないか。
彼は苦しみ、自らの不敬に苦悩した。
だが悩みの海にたゆたうのは、他ならぬあの天使の姿。
眩しく白んじる瞼の裏に、ゆらりと黒い影がよぎる。不思議なことにその影は絶えず輝いているのだった。
光に焼けた青年の瞳は、その黒いシルエットを喜んで迎え入れた。黒い靄は徐々に人影の形を模し、彼の心に語りかけてくる。陽炎のごとく不安定に揺らめきながら、影は甘い声でこう囁くのだ。
イーノック、よくやったな、と。
青年は苦悶を振り切るように頭を振った。髪が乱れる。
違う、と彼は自責する。こんなことを彼――ルシフェルは決して口にするはずがない。あの人影は自分の弱い心が生み出した都合のいい妄想だ。天使に恋焦がれるあまり創り出した幻影だ。イーノックの心臓は吐き出されんばかりに鼓動する。
しかし、ああ、なんということだろう。
青年は天使の幻影から先へ進むことができないでいる。
「神よ」
半ば絶望に沈んだ声で彼はつぶやいた。声はしわがれ、まるで五十も余計に年を取ったようだった。
「全知全能の神、全ての父よ。あなたにはきっと、私のこの浅ましい想いさえ容易くお分かりになるのでしょう」
彼は何も言わない。台座に身を預けて、自らの目の前にひざまずく小さな生き物の声に耳を傾けているだけだ。
「恐ろしいことに、私は彼を――大天使ルシフェルを恋い慕っているのです。
あなたがお創りになった中で、彼は最も素晴らしい存在に思えます。彼の姿を思い描くたび、彼の声に導かれるたび、どれほど私は旅の孤独から救われたことでしょう。私は彼を通してあなたの存在を感じるうち、いつしか彼自身を愛するようになってしまったのです」
『お前が饒舌に語るとは珍しいね。明日は雪を降らそうか』
茶化すように彼は言ったが、そのくせ真剣な面持ちを保っている。
イーノックは彼の表情を見ることは決してなかった。しかし、流れる空気の中に張り詰めた気配を感じていた。
『お前の選択を聞こう、イーノック。
あの子、ルシフェルを選び、禁じられた破滅の道へと進むのか。それとも子孫に光を残し、最期まで私と共に歩むのか』
「是非もありません」
敬虔な青年は苦しげに吐き出した。元より選ぶ余地などないのだ。
恋の苦しみがイーノックを苛む。彼の身体はあちこちやたらと刺されたように痛んだ。
「私はあなたの召使いです。好みで捧げられるものならば、惜しみなく全て差し出しましょう」
祝福の光は強さを増す。イーノックの褐色の肌はますます焦げていくかに思えた。
神は愛おしげに目を細めた。わが子を慈しむ心が彼の中に満ちていた。
なんという不完全で、不器用な生き物だろう。青年の純粋さは既に聖人の域を超え、神である自分にさえ迫り始めている。そのことにイーノック自身が気付いていないことこそ、彼が彼である所以なのだった。
『原罪を背負う人間として生まれ、それでも尚聖なる存在へと近づく者よ』
荘厳なる響きを乗せ、神は告げる。
『お前の慎ましい魂を讃えて、天使としての名を授けよう。
――メタトロン。
お前は人間である身のまま、大天使の名を得る者となる』
「メタトロン……」
イーノックは繰り返した。現実感はまるでなかった。この授けられた名が自分を指し示すことになるとは到底思えず、彼は口中でもごもごと単語を転がした。
『最良の選択を続けたお前への祝福として、私はお前の願いを二つ聞き届けよう。
ひとつは旅を終えた義人イーノックへ。
ひとつは幸福の為に死にゆく天使メタトロンへ』
彼は考え込む。
ルシフェルの姿は相変わらず焼きついて離れない。ともすれば酷く欺瞞に満ちた願いを口にしそうだったので、彼は慎重にならざるを得なかった。
ルシフェルの心を我が物にしたい、とは思わなかった。そんな幻想ごっこをいつまでも続けたところで虚しくなるだけだ。
ただイーノックはもっとルシフェルと話がしてみたかった。共に美しいものを見て、美しい、と言い合う時間が欲しかったのだ。それくらいであればあの高潔な大天使を揺るがすこともないだろう。イーノックは端からルシフェルから愛されることなど期待してはいなかった。
だが、このまま地上へ降りれば、恐らく私は後悔することになるだろう。青年は思った。将来娶る女性にも顔向けできず、息子を愛してやることすら難しいだろう。
やはり、このままでは終われない。
「私にどうか、ルシフェルと共に過ごす時間を」
搾り出すようにイーノックは願った。
「あなたは七日でこの世界を創られた。私は敬意をもってそれにならいましょう。
どうかあと七日だけ、私に天界で過ごす時間を下さい。その後私は喜んで地上へ降り、誇りと共に死にましょう」
太陽の匂いが強くなる。青年は激しく燃え盛る炎の前に立たされているようだった。
『その願い、叶えよう』
重い声で神は告げる。
『義人イーノックの願いとして、お前を七日ここへ留めよう。
では、もうひとつの願いは何とする?』
イーノックは浅く息を吸った。望む答えは既に決まっている。
「地上へ降りた私に、忘却を」
今にも掻き消えそうな声だった。イーノックは掠れた声でそう口にし、それから苦しげに微笑んでみせた。
「私の足が地上に触れたら、私のこの想いが全てなくなるよう、忘却を。
私はこの恋心を捨て、未来の妻と息子を愛し、己の天寿を全うしましょう」
さあ、と優しい風が吹いた。
柔らかさのあまり、青年は堪らず嗚咽をあげてしまいそうだった。その願いは彼にとって並ならぬ努力の結果だったのだ。
今までイーノックを支え、構築し、強くしたのは大天使ルシフェルだ。その彼を忘れ去ることとは、すなわちイーノックにとっての四百年を捨て去るのと同じだったのだ。
『叶えよう』
変わらぬ調子で神は言う。
『大天使メタトロンの願い。
来たるべきそのときには、お前の想いを貰い受けよう』
イーノックは笑った。全てに整理をつけた、くしゃくしゃの笑顔だった。
彼が閉じたままの目の端から、銀の雫が一筋落ちた。
話を終えた青年は、扉までの道を手探りで這い出ることにした。
来た道を戻ることがこれほど難しいとは。目を瞑ることで方向感覚は失われている。イーノックは赤子がするように四つん這いで進んだ。みっともない格好ではあったが、閉じた瞼は既に涙で糊付けされてしまっていた。
こつん、と何かが指先に触れる。硬い感触だった。何も無いはずの空間だったが、どうやら突如出現したらしい。イーノックはおそるおそる指先を動かし、そのフォルムを確かめてみる。
「くすぐったいよ」
低い声がした。
待ちわびた声に青年の胸は否応なしに高鳴る。誰が目の前に立っているのか、姿を見なくともすぐに分かった。自分を見下ろす赤い眼差しを皮膚で感じる。
「ルシフェル」
イーノックは頬をほころばせる。
「君が触っているのは私の靴だよ。
随分長くかかったじゃないか。どうだい、私に隠れて内緒話に興じた気分は」
「悪くなかった」
書記官が予想外の返答を投げて寄越したので、ルシフェルはころりと目を丸めた。
「君にしてはやけに気の利いた答えだ。これはますます話の内容が気になるな」
金髪の青年はただ笑うだけで、答えをうやむやに誤魔化した。
大天使本人に、神と交わした約束の内容を伝えるつもりはなかった。仮に伝えたところで何が変わるわけでもない。天使の気を惹くこともないだろう。その日が来れば失せる身なのだ。口をつぐんでいるのが美徳だろう。
ルシフェルは書記官の黙秘が面白くないようだった。
「ふうん」
さも気のない素振りを装い、天使は眉を吊り上げる。
それから足元に這いつくばる男の耳をちょいと摘まんでみせた。
長い指が容赦なく褐色の耳たぶをつねる。予想だにしない部分の痛みに、思わずイーノックは目を開きそうになってしまった。
ルシフェルは手を離す。哀れ青年は何をされたか理解できず、きょろきょろと痛みの行方を追っている。ようやく大天使は笑い出した。自分の悪戯に容易く引っ掛かる書記官は愉快だった。
「ほら。出口を探しているんだろう。連れて行ってやろうじゃないか」
ルシフェルは青年の太い腕を握った。
「ん……なんだ、まだ肉の身体のままでいるのか。てっきり彼が君をアストラル体にしてやると思っていたんだが」
天使の手はどこかひんやりと冷たい。触れられる慶びに感謝しながら、イーノックは大天使の手首を取り返した。
「だが、名を貰ったよ」
「名とは?」
「神は私へ、大天使メタトロンという名を下さったんだ」
「へえ! 良かったじゃないか」
あからさまに嬉しそうな響きを込めてルシフェルが応じた。彼はにこにこと目尻を下げる。天使の顔全体が、なにより喜ばしいことだ、と言っていた。
「それはおめでとう、イーノック。あ、いや。これからはメタトロンと呼ぶべきか」
書記官は天使にすがって立ち上がった。
二本の足が床を踏む。床は先程までと同じく雲のように柔らかかったが、もう足を取られることはない。イーノックはしっかりとした足取りで天使の導きに応えた。
「頼むから、そのままイーノックと呼んでくれ。まだ新しい名に慣れていないんだ」
「名などそのうち慣れるさ」
「どうかな。それでも私は、あなたにはイーノックと呼ばれていたいんだよ」
ルシフェルは小首を傾げた。呼び名に執着する心は、大天使には理解出来ない感覚だった。
しかし彼は書記官が天使の名を持ち、これから永遠に神と共に在ろうとしたことを素直に喜んでいた。彼が天使の名を得たことはルシフェルにとって、書記官への印象を前よりずっと良くさせた。
だから大天使は黒髪を僅かに揺らしただけで、彼の言い分を聞き入れた。
「君がそう言うならそうするが」
「ありがとう」
イーノックはほっと救われた気分でいた。
「礼には及ばないよ。大したことじゃない。……さ、着いた。もう目を開けてもいいぞ」
言われて青年は目をこじ開ける。長らく閉じていた目の淵には涙の塩が固まっており、パリパリと不快な感触がした。
目頭を擦る。眩しさに眩暈を起こすかと思っていたが、存外平気なものだった。それとも今まで、眩むほどの光の中にいたからだろうか。
するり、と掴まれていた腕が放される。
黒髪の天使は折れそうに細い足で器用に立っている。彼の背後には再び白オニキスの扉が立ちはだかっていた。
取っ手のない、つるんと滑らかな見た目。穏やかな白は大天使の黒を鮮やかに浮かび上がらせる。白と黒、見事なコントラストの中に二つの赤い瞳が光っていた。
「ご苦労様。じゃあ、私は戻るよ。積もる話もあるからね」
ひらりと手を振る。
ありがとう、とイーノックはもう一度礼を繰り返した。
天使は大らかに笑った。それが仲間に向けるような眼差しだったので、青年は堪らなく感じ入ってしまった。初めて彼の温度に触れられた気がしたのだ。
ほら、どいたどいた、とルシフェルがおどけた調子で言う。
「肩書きは天使でも、身体は肉のままなんだろう。新米大天使め。また私がここを開いたらどうなっても知らないぞ」
「あなたは怖いことを言う」
イーノックは薄く微笑んだ。
「注意してやるだけ有り難いと思うんだな」
「なら大人しく部屋に戻ろう」
「賢明な判断だ」
「じゃあ」
「ああ」
褐色の男は簡潔に別れを告げ、ゆったりと踵を返した。そのままルシフェルへ背を向ける。後ろ髪を引かれる想いがした。
彼は一秒でも長くあの大天使と共にいたかったのだ。残されている時間は思うより少ないのだろう。
しかし、彼の時間は他ならぬ彼のものだ。イーノックはそれをわきまえていた。少し聞き分けが良すぎるほどだった。
ひとり回廊を進む。見慣れぬ場所ではあったが、そもそも天界には一本道しか通ってはいないのだ。
どう進もうと、いつかは目的地へ辿りつける。己が行く道を選択することなどしなくて良いのだ。
回廊の両端にそびえる石柱を横目に、イーノックはぼんやりと歩いた。押し込めていた旅の疲れがようやくぶり返してきたようだった。
彼は虚ろな目で回廊の床を見る。石畳には継ぎ目もない。天界は隅から隅まで完璧に創られているのだった。その上を不完全な自分が歩いているのだと思うと、イーノックは無性に可笑しかった。
天使に恋をするような、不器用な人間が。
知恵の実をかじった後のアダムとイヴも、もしかするとこんな気分を抱えていたのだろうか。浅ましい想いを抱えた者にとって、この天界は冷たい場に映るのだった。
それでもこの想いを捨てることなどできるものか。ルシフェルを乞うようになってから、もう三百年以上が経っているのだ。諦められるものだったのなら、とうに諦めている。
「なんと、罪深い……」
ぽつりと呟く。その呟きを聞く者は誰もいない。
イーノックは肩越しに振り返った。そして通ってきた回廊の奥で、爆発的な光の奔流を見た。
あの扉が再び開かれたのだ。
遥か向こうにも関わらず、白い煌めきは青年の網膜を襲う。
うっ、と目を伏せる寸前、彼は確かに見た。
濁流の中でも平然と経つ、黒いシャツの男の姿を。
次に彼が目を開けると、回廊の奥は静まっていた。扉が閉じられたのだろう。あれほどの光の波が嘘のように引いている。
「――ルシフェル」
イーノックはぐっと拳を固めた。
大天使の姿は既にない。後には豆粒ほどの大きさで、白オニキスの扉が見えるのみだった。
→次へ
▲戻る
|