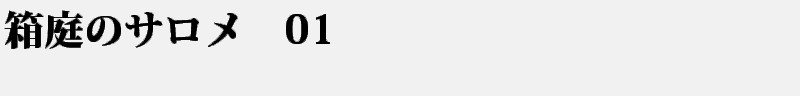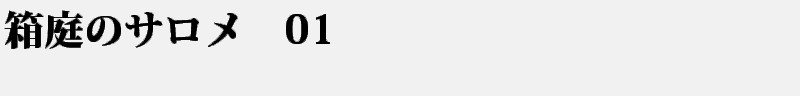|
《背徳の塔》一階に巣食う堕天使エゼキエルを撃破する寸前、イーノックは躊躇ったようだった。
エゼキエルの壊れかけた老体は、未だ至ったことのない『死』を迎えるため、だらりと投げ出されるがままとなっている。器から流れ出す出来損ないの血液の勢いは弱まることがない。しかし、それでも『死』が彼女に訪れないのはエゼキエルがヒトではないからだった。
イーノックが繰り出す斬撃だけが、哀れな堕天使に終焉を与えることができる。しかし、彼はそうしない。そうすることができない。荒い息を隠花植物のようにひそめて、血にまみれた老婆の白髪を視界に収めている。
神の力で穢れた肉体を引き裂く。
ただそれだけのプロセスを、人間であるイーノックは酷く畏れたのだった。
天使殺し。原罪を背負った穢れた人間の分際で、お前は聖なる生き物を殺すのか。お前は天使の首を刎ねる鎌だ、イーノック。
自らを執拗に責め立てる声が彼を何重にも苛む。振りかぶったままのアーチをどこにもやれないまま、青年は刃物で胸を刺されたように呻いた。
「早くやってしまえ、イーノック」
目の前で繰り広げられている光景の退屈さに、ふあ、と欠伸をしながら、赤い目の水先案内人は手元の携帯電話をカチカチと弄っている。
青年が躊躇いを見せているのは、天使にとってなんとも不快な光景だった。一刻でも早く片をつけさせて、イーノックを次の段階にまで召し上げなければならないのだ。それがルシフェルに課せられた使命。そのためには、躊躇なく目の前の踏み台を踏みつけて貰わねば困るのだ。
アーチを握る彼の手がぶるぶると震えている。こめかみから滲むねっとりとした汗が、首筋を伝っていく。
「で、でき、ない」
寡黙な男は言葉をどもらせ、また一層顔を蒼ざめさせる。ルシフェルの片眉が神経質にぴくりと吊り上がった。血の気の引いた顔は死人のようで、目の前の老婆と彼のどちらが黄泉に向かうのか判別がつかなかった。
「わた、私には、エゼキエル様を手に掛けるなど――私のようなものに、私のような人間に、他者を裁く権利などあるはずが」
「選んだのは君だろう」
氷矢のような声に射抜かれ、イーノックは呼吸を止めた。
ルシフェルの視線は既に携帯電話の液晶などには向けられておらず、じっと青年を正面から見据えていた。濁った瞳は人外のものだ。これほど恐ろしいまでに美しい瞳が、下界に落ちているものか。葡萄色の目はイーノックにいやというほど己の矮小さを突きつけてくるようだった。どこまでも冷ややかな、体温のない視線。
辺りには壊れかけのエゼキエルの肉体が吐く、ひゅうひゅうとした息遣いだけが響いている。その場に咲き乱れていた育ち過ぎた植物達も、今ではもう枯れゆくばかりだ。
「下界を救う道を選んだのは君で、君を選んだのは神だ。
自惚れるなよ、人間。君はもうどこへも行けやしないんだ。神の御心に適うそのときまで」
掛けられた言葉に感情はない。あるがままの真実だけを淡々と述べているのだった。だから余計にイーノックの精神は散り散りに乱れ、今にも金の髪を引き抜いてしまいそうになる。
イーノックの精神は十分に熟していたが、彼の魂は恐ろしいほどに純粋だった。自分の母の影がちらつき、重なり、彼を惑わせる。堕天使といえど人の姿を取っているのだ。骨があり、肉がついている。切り裂けば血が噴き出し痛みもあるだろう。ああ、なぜ、寄りにも寄って何故人間の老婆の姿など!
畏れと感傷がない交ぜとなり青年を襲う。大粒の涙がとめどなくぼろぼろと零れたが、腕を組んだルシフェルはといえばさも鬱陶しそうに舌を打っただけだった。煽るように片手を振り、吐き捨てるように言う。
「いいんじゃないか。君に浄化ができないのならば、彼自らが下界を一掃するだけさ。誰も君を責めやしないよ。
どうせ元より定まっていた運命だ。こんなことはさっさとやめて、流れるがままに任せておけばいい」
諦観に満ちた表情で、溢れる涙を拭うこともせずにイーノックはかぶりを振る。
違うのだ。そうではないのだ。そんな気持ちと決意で、自分はこの旅を志願した訳ではないのだ。
いくらそう主張したくとも、大天使は残酷なほどあけすけだ。
じゃあ君はどんなつもりだったんだい。
問われれば、返す言葉はない。青年は厚い唇を一文字に引き結び、ぐっと前歯で噛み締めて押し黙った。俯いたところでルシフェルの追及が止むはずもない。
ほら、さっさととどめを刺せよ。革靴の爪先が偽りの地面をこつこつと叩く。
エゼキエルの手がイーノックの足首を掴んだのはそのときだった。
「!」
青年は老婆の節くれだった手に捕らわれ思わず仰け反った。無様に這いつくばるようにして、エゼキエルは彼の顔をなんとか見上げている。顔面は所構わず血に汚れていたが、二つの目はまだ見えるようだった。弱々しい赤子のような手に恐怖を感じ、振り解こうとしたが身体は動かない。蹴り飛ばすことなどできるはずがなかった。
エゼキエルはイーノックを眺め、ゆっくりと微笑む。
「イーノックに触れるな」
左手を槍のように突き出して、ルシフェルが彼女に告げる。静かな怒気を孕んだ声だ。突きつけた左手の先からは神気が氷柱のように形を成して、老婆の喉元を狙っている。かつての同輩を憐れむでもない、蔑んだ眼つき。
「今まで散々好きにやってきたんだ。もういいだろう。
敗者は大人しく首を差し出せ」
首元に突きつけられた刃も、死を待つだけの堕天使にとっては物の数にもならなかった。エゼキエルの目はイーノックを捕えたまま、柔らかく細められる。そこにもはや狂気じみたものは浮かんでおらず、ただ澄んだ母性愛のみが宿っていた。
血に噎せながら、彼女は乾いた唇を開く。わなわなと震える唇は多量の息と共に、ようやく言葉を紡ぎ出した。
「イーノック。あなたは……選ばれてしまったのですね」
「耳を貸すな、イーノック」
「あなたは選ばれてしまった……私は、あなたの糧となるのですね。
私という存在を糧とし、あなた自身を生贄として、あなたは一体何に成らされるのですか」
「イーノック!」
エゼキエルの濁りゆく金の瞳は優しかった。満月の眼差しに見出され、彼はその場に立ちつくした。彼女の紡ぐ言葉の意味は何一つとして分からなかったが、そこに何か真に迫るものを感じ取って、青年はぽつねんとそこに立っていた。ルシフェルの声も今は遠く、鯨の残響のように辺りを漂っている。
枯れ枝のような指がくるぶしを撫でる。生命を愛おしむような手付き。
「私はあなたを憐れみましょう、イーノック。そして祈りましょう。あなたの旅が、他ならぬあなた自身によって閉じられることを。
ねえ、約束してくれるでしょう」
それは母の忠告のような響きを帯びた問い掛けだったので、青年は思わず頷いてしまった。ひとつ首肯すると、老婆は皺だらけの顔をくしゃくしゃに崩して、そうっと掴んでいた手を離した。僅かな温もりが風にさらわれていく。
彼が意味も分からずに行った同意は、彼女に最期の覚悟を決めさせたようだった。エゼキエルは今度こそ自分の意思で身体を投げ出して、イーノックの決断に全てを委ねた。瞼が彼女の瞳を覆い隠していく。
あれほど雑音が混ざり細かった息も、今は落ち着き始めているようだった。ただ訪れるべき瞬間を待っている。
エゼキエル様、とイーノックは口内で名前を呼ぶ。音のない声は霞んで消えていく。
「早くして頂戴。肉の身体は、不便だわ」
書記官は静かに睫毛を伏せた。黙祷のようにも見えた。ルシフェルは突き出していた左手をゆるゆると納めて、ジーンズのポケットへと押し込む。
アーチは既に青年の身体に馴染んでいた。彼の意思ひとつで形を変え、碧いエネルギー体で作られた刃を剥き出しにする。
長い戦いの中で、イーノックはある経験を幾度となく繰り返していた。誰かを苦しめて死に至らしめてしまった経験だ。神の武器は最初のうちは加減が分からず、無闇に肉体を傷つけてしまうということが多々あったのだ。
だからその分、今では安らかに魂を剥ぎ取ることができる。純粋に、できる限りの想いやりを持って、最小限の痛みで相手を浄化することができる。
イーノックは心優しい青年だった。それゆえに堕天使エゼキエルの最期に対しても、魂を引き剥がせる最小限の斬撃しか加えなかった。
痛みに呻く声すらあげることなく、エゼキエルの肉体は死んだ。
刹那満ち足りた微笑みが彼女の頬の上を横切ったが、それをまじまじ確認する間もなく頭部は土となり崩れ落ち、それから黒く焼け焦げた灰となってしまった。灰は無風の中さらさらと渦として舞い上がり、霧散する。
紫じみた黒い光の塊が《背徳の塔》を抜けて行くのも同時の出来事だった。あれはエゼキエル様の堕ちた魂だ、とイーノックは確信していた。魂は空を覆う漆黒の帳を抜け、天界の牢獄に囚人となって繋がれるのだろう。
半ば放心状態で光の行方を追っていた青年の背中を、気つけのようにルシフェルがぽんと叩く。あまりに気軽な呼びかけだったのでイーノックは反射的に飛びのいた。大天使は先ほどまでの冷徹な態度はどこへやら、飄々と両手を広げて一仕事終えた彼を歓迎している。
「やあ、お疲れ様。一時はこのまま旅をやめてしまうのかとでも思って心配したよ。君の功績には彼もさぞかし喜んでいるだろうさ。
今日はこのまま拠点へ戻って、明日は安息日としよう。それくらいは猶予も、
……っと、すまない」
周囲に電子音が鳴り響いたので、ルシフェルは賛美の言葉を止めておもむろに携帯を取り出した。
ディスプレイに映る発信者の名を見ると、えも言われぬ表情を浮かべる。苦虫を噛み潰したような、奥歯に物が挟まったような顔だ。
イーノックは殺しの余韻から抜け出すことができないまま、ぼうっと胡散臭い大天使を眺めている。呆けた人間をそのまま横へ置きながら、ルシフェルは仕方なしに受話ボタンを押した。黒い髪を掻き上げ、耳を押し当てる。
「もしもし。君か。見ていたんだろう? 今終わったよ。ああ。大丈夫だ、全てうまくいってる。……なに? そうだよ、全てだ」
男は通話しながら首筋をぼりぼりと掻いた。通話相手の正体は知っているが、ここまで面倒臭そうに受け答えをしているルシフェルの姿は初めてだった。彼は声をひそめようともせず、イーノックが預かり知ることのない話をしている。
エゼキエルの残骸は既にその場から跡形もなく消え失せていた。彼女のいた痕跡がもうどこにも見当たらないので、書記官は儚んだ。彼女が愛した草木や動物も、今は成れの果てとなってそこらに転がっている。及ぼされた強過ぎる成長は根を張った毒のようなものだ。宿主を失えば毒は即座に全身を駆け巡り、すなわち死が待っている。
暫くの間ルシフェルは曖昧な相槌を繰り返していたが、ある瞬間にぴくりと片眉を上げ、口角を落とす。冷たい溜め息が吐かれた。
「悪趣味だな。君のお気に入りは、君が求めるように育っているよ。何度言わせるんだ。そこまで進行状態が心配なら私になど任せず、君が付き添えばいいだろう」
ただならぬ口調はイーノックの肩を萎縮で縮こまらせた。まるでこちらが叱られているような気分になる。責苦から逃れるように視線を落とすと、これには通話中の大天使も気付いたようだった。はたと青年を見つめると気まずそうに眉間に皺を寄せる。
ほんの少しだけ声のトーンを落として、ルシフェルは冷静にまくし立てた。
「ともかく、大丈夫だ。任せておいてくれ。……イーノックが怖がるだろう」
ああ。ああ、それではな。
半ば強引に会話を打ち切り、ルシフェルは携帯電話をぱたりと折り畳んだ。そして怯えた小動物のような目をしている男に両手を広げる。敵意はないよ、とでも言うように。
そして実際に彼は、すまない、と口にした。
「待たせたな。
彼は案外多弁でね、些細な話題でもすぐに長くなるんだ。天界で暇を持て余しているんだろうな、何せ彼はそこから動けないから。
まったく、参ってしまうよ。天使職も楽じゃない」
それから微笑みが浮かべられる。それが愛想笑いであるのかは判断がつかなかった。大天使の両腕は全てを受け入れるように広げられているが、大いなる純白の翼の姿を彷彿とさせて、イーノックは見せつけられる強大な力に畏れを抱いた。分かっていたはずのことではあるが、ルシフェルは人間ではないのだ。伺い知れぬものを畏れるのは人間に科された本能のようなもので、だからイーノックは安易にその腕を信用しなかった。
自らが差し伸べた手が取られなかったので、ルシフェルは薄く唇を尖らせる。純粋に拗ねたようだった。広げた腕をゆっくりと閉じ、小さく肩を竦める。その行動さえも今の青年にとっては種の壁を感じさせるものに過ぎなかった。
大天使ルシフェルの考えを先読みすることはできない。あのエゼキエルを前にしたときの態度も、単純に善と悪を感情抜きで識別しているだけなのか、それとも天使という種族はそういうものなのか。それとも、他に何か意図があったのだろうか? イーノックには何も分からなかった。
ただ目の前に立っている戦友との距離が開いてしまったのはひしひしと感じていた。距離を置いたのは他ならぬ自分の方だ。
《背徳の塔》は全てを疑心暗鬼にさせる効果を持っているように思えた。少なくとも、イーノックの心はずぶずぶと重く沈んでいくようだった。これ以上ここにいるのは得策じゃないな、とルシフェルは呟いた。用も済んだんだ。早く帰ろう。そして火を熾したら、何か温かいものでも淹れようじゃないか。これはルシフェルが今日切り出した提案の中で最も素晴らしいものに思えたので、イーノックはこくりと頷いた。
堕天使を殺したアーチの刃はさらけ出されたままだったので、書記官は静かにそれを格納した。エゼキエルの血の痕は残っていない。
人間は自らの足で、来た道を引き返すことにした。憂鬱な足取りは塔の地面にめり込んでいくかに思えたが、なんとか彼は歩くことができた。天使はひょろひょろと浮いたような歩調でイーノックの隣についている。
帰路に主だった会話はなかった。イーノックは押し黙り、大天使もあえて声は掛けずにいる。今の彼にとっては心地良い沈黙だった。書記官は初めての堕天使殺しの後味を気が済むまで憂うことができた。帰り道に広がる光景は来たときとは打って変わり、しんと静まりかえっている。枯れた花々を踏み締めながら一人と一匹は、勝利の行進というにはあまりにも粛々とした歩みを続けている。
太陽は黒い帳に覆い隠されているから、塔の外は常に闇夜のようだった。
日陰に生きる僅かな草花を摘んで、ルシフェルは立派な薬湯をこしらえた。熾した焚き火で湯を沸かし、淹れられたそれは面妖な香りを発している。天使には食欲が存在しなかったので、薬湯には味の好みなど関係なしに、ただ効果のある薬草だけが選ばれた。
渋くて苦い煮出し汁を、イーノックは文句も言わずに啜るように飲んでいる。
冷えた身体が温まってくると血行が良くなったのか、微かな擦り傷までがじんじんと痛み出した。止血効果のある葉を揉んで柔らかくし、傷口へと押し当てる。即効性はないはずだが、目先の痛みは引いていくような気がした。もっとも、プラシーボ効果である可能性は否めないが。
「少し眠ったらどうだ」
燃えさかる火の番をしながら、ルシフェルがそっと声を掛ける。それが普段通りの想いやりに満ちたルシフェルの口調だったので、イーノックは少し警戒を緩めた。
「気分が昂ぶって眠れないんだ」
「ならせめて目だけでも瞑っているといい。睡眠の真似事をするだけでもだいぶ疲れは取れるだろう。
私が見張りをしていてやるよ」
ありがとう、とは答えたものの、素直に瞼を下ろす気にはなれなかった。ひやりと冷えた地面はしっとりと濡れている。とても身を横たえる気は起きない。
イーノックは膝を立てて、銅のカップを横へと避けた。注がれた薬湯は三分の一以上が残っていたが、既に舌がその味を受け付けなくなっている。残りは明日の自分に預けることとして、枝で焚き火を煽ることにした。炎の扱いは天使よりも書記官の方が巧い。
「眠れるようになるまで、話に付き合ってはくれないか」
ぽつり、イーノックが似合わないことを言い出したので、ルシフェルは怪訝そうな顔をした。
「驚いた。口下手な君が自分の話をしたがるとは。
折角の安息日だが、明日は雨だな」
天使はそう言って軽く茶化したが、話を聞くつもりはあるようだった。胡坐を組み直して、頬杖をつきながら身を乗り出す。仄暗い闇の中、二つの紅い瞳が猫のように爛々と輝いている。
焚き火の炎は十分に勢いを保っている。先ほど食べ終えた魚の骨の隣に枝を置き、イーノックは立てた膝を抱える。露わになっていた部分の肌が温まった太ももに冷たく貼りついた。
「虫の息のエゼキエル様を見たとき、」
「あれはもう君より低位だろう。呼び捨てにしろ。言葉は君を縛る」
「……エゼキエルを見たとき、私は亡き母の姿を思い出してしまった。母の死の間際の眼差しを二度も見させられたようで息が詰まったんだ。あの憐れみを湛えた眼が、今でも焼きついて離れない」
イーノックは両手を広げ、飴色の手の平をじっと見つめた。今にもそこから血生臭い臭いが漂ってくる気がして、ぎゅうと拳を握る。
「私が彼女を手に掛けた」
「全て君の勘違いだよ」
ルシフェルは事もなげに声を掛けた。あのときの非情な彼はどこへ行ったのか、向けられた表情は慈愛と憐憫に満ちている。大天使は穏やかに右手を上げ、そろりとイーノックの頭を撫ぜた。ごわついた金の髪が白い指先に絡め取られる。書記官はほんの微かに身を引いたが、やはり撫でられるがままでいることにした。たおやかな指が青年の髪をすくっては、戦闘で醜く絡まった部分を優しくほどく。
「あれは君の母ではないし、君は母を殺した訳じゃない。君は世界をあるべき姿に戻しただけだ。穢れを祓い、君の清らかさはまた一層強くなる。
今は堪えがたいほど苦しく思うかもしれないが、それも次第に消えていくよ」
「本当だろうか」
子どものように不安がって、イーノックは頭を天使の手に擦りつけた。おぼろげな体温でも今は心地良かった。ルシフェルからはいい香りがする。血の臭い以外の、何か清らかな香りだ。
「ああ、保証しよう。君はこれ以上、彼女に苦しむことはなくなる」
そのとき。
ルシフェルは少しだけ、本当に少しだけ、哀しそうな瞳をした。けれどその沈痛な面持ちを見ることはなく、イーノックは疲労困憊した仔犬のように撫でられ続けていた。
大天使の保証は何にも増して心強いものに思えた。この痛みは、やがて薄れて消えていくのだろうか。エゼキエルを、あの母性愛に堕ちた哀れな老婆を、感傷なしに思い返せる日はいつ訪れるのだろう。
ゆるり、目を閉じる。ルシフェルの体温を感じている間は、瞼を下ろしても悪い夢を見ないで済む気がした。
「私を憐れんでくれ、ルシフェル」
掠れた声でイーノックが切望する。
「いつでも君を憐れんでいるよ」
大天使は絶えず人間の青年の頭を撫でながら、囁くようにして甘く呟いた。降ってくる声は心から発せられたように聞こえた。だから青年は赦されたような気分になって、小さく頭を垂れる。
「私が眠るまで撫でていてくれるかい」
「そうしよう。君が望むなら」
イーノックは仄かに微笑みを浮かべて、未だ見えぬ眠りの世界へゆるゆると落ちていく。ぱちぱちと乾いた薪が炎に爆ぜる音が彼を誘った。立て膝をついた体勢のまま、イーノックは静かに息を整える。張り詰めた姿は棘のついた実のようだ。
ルシフェルは饒舌な口を引き結びながら、静かに彼を撫で続けていた。いつまでも、いつまでも、イーノックが寝入るまで、そうっと金のつむじを撫で続けていた。
→次へ
▲戻る
|