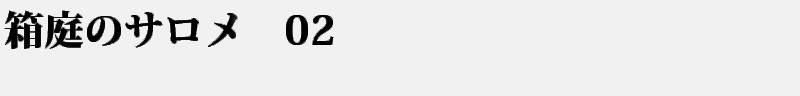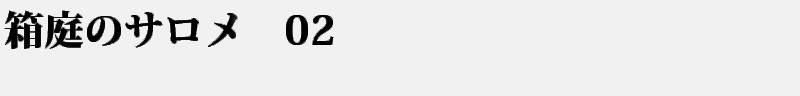|
神は六日で世界を創り、七日目を安息日とした。ルシフェルとイーノックの旅もそれに倣って、六日《背徳の塔》へ通っては七日目を休息の日とした。だから本来は今日も浄化に勤しむべきだったのだが、堕天使を一匹捕縛できた昨夜を祝い、今日に限っては例外と見なすこととした。ルシフェルの提案により、臨時の安息日となったのである。書記官の疲労具合を見れば賢明な判断だった。
青年はまだ眠っている。安らかに瞼を閉じた顔の上には、もう失望の色は残っていなかった。大天使は一息吐いて安堵を表したが、本当は今でも気掛かりに思っていた。目覚めた瞬間、この男は一体どんな反応を取るだろう。流石の大天使ルシフェルにも、こればかりは予想がつかなかった。天使を殺した人間など、後にも先にもイーノックしかいないのだから。
『――……』
旅の出立前、神が告げた言葉が頭をよぎる。ルシフェルは双眼をそろそろと閉じた。
大天使はこの哀れな男に、ある秘密を隠していた。それは息を呑むほど重要な事項だったが、告げることは叶わない。神との契約によりルシフェルの口は封じられている。天使は人間とは違う。選択の自由は持たされていない。だからこうして大人しく口をつぐんでいるのだ。
一言で表すのならば、彼の『成長』に関する秘密だ。
神の言葉に従えば、変化は緩やかに訪れるはずだ。緩やか、とはどの程度であるのかは分からないが、すぐにという訳ではないはずだ。少なくとも、天使はそう考えている。
目を開ける。
この男はまだ覚えているだろうか。昨晩起こったあの捕縛劇を。そして感傷を呼び起こし、顔を曇らせることができるだろうか。
それとも――。
「う……ん」
イーノックが唸る。
ルシフェルはハッとして息をひそめたが、青年は寝返りを打っただけだった。そのまま暫く様子を見ていたが、目の前で褐色の腹回りをぼりぼりと掻き始める始末だったので、天使はほっと息をついた。むにゃむにゃと寝言を食む口元は無垢そのものだ。起こしてしまったか、と一瞬でも案じた自分が馬鹿馬鹿しく思えて来て、ルシフェルはふと口端を緩める。だが、またすぐに気を張った。金の光を宿した睫毛は、ミルクの香りがする甘い眠りに委ねられたままでいる。彼が安らかな眠りを貪ることができるのは良いことのはずだったが、このときばかりはルシフェルも素直に喜ぶことはできなかった。
ルシフェルはゆったりと目を閉じ、昨夜の書記官が漏らした言葉を反芻した。
亡き母の姿、か。
赤目の天使はイーノックの母を知らない。イーノックと初めて出会ったときには、既に彼は天界唯一の人間の書記官として名を馳せていた。時を遡りさえすれば、彼の母を見ることなど赤子の手を捻るよりも容易だったが、ルシフェルはそうしなかった。単純に興味がなかったのである。今のルシフェルにとっては現時点のイーノックさえサポートできれば良かったし、彼の持つ過去にもさしたる興味はなかったのだ。
そう。ルシフェルにとっては、現時点のイーノックが一番大事なのだった。昨日までの、人間らしい弱さを持ち合わせた臆病なイーノックを気に入っていたのだ。
「……ふん」
だが、もはやどうすることもできはしない。エゼキエルの死により、彼の時計の針は動き始めた。あとは結末までを刻み続けるだけだ。それがイーノックの選択ならば、私が支持しない訳にはいかない。
刹那、大天使はあの冷徹な目、エゼキエルの死を前にしたときに放った視線でイーノックを睨んだ。大理石像のような碧い美しさを、ひやり、輝かせる。しかしそれも束の間、またいつもの飄々とした顔付きを作り直した。赤い舌で上唇をひと舐めし、天使は両手を腰へと当てる。
イーノックが自然に目覚めるまではまだ時間が掛かりそうだ。今日だけはこのまま寝かせておいてやろう。
ルシフェルはそろりと踵を返しかけたが、はたと立ち止まる。
青年の身体の上に掛けた麻のローブがめくれている。寝返りの際に剥がれてしまったのだろう。ルシフェルは僅かに目尻を下げ、再びローブを毛布代わりに掛け直してやった。
肝心の青年は礼も言わず、眠りこけたまま眉頭を爪で掻いている。己の行動に納得が行くと、天使は今度こそその場から離れた。
安息日にはいかなる仕事もしてはならない。あらゆる火を焚いてはならず、薪を集めてもいけない。当然料理などできないから、ルシフェルは昨夜用意しておいた焼き魚を枯れ葉の下から取り出した。串刺しにされ焼かれた魚の口からは焦げた木の枝が突き出している。
死体をためらいなく食物と呼ぶのも、今のルシフェルにとってはもう慣れたことだった。数匹の魚に、平たく硬い数枚のパン。これがイーノックに用意された今日一日分の糧だった。大の男が腹を満たすには少な過ぎる量に思えたが、安息日のイーノックはこれ以上何かを口にすることはないのだった。
「食わねば筋肉が衰えるのだがなあ」
ルシフェルがひとりごつ。恐らくは節制を心掛けているのだろう。
「まったく、どこまでも聖人だよ。あいつは」
大天使にそんな台詞を言わしめたのは恐らく書記官が初めてだろう。イーノックはあらゆる聖人の中でもとりわけ敬虔で、更に言うならば愚鈍だった。
せめて新しい茶でも淹れてやろうか、と湯を貯蔵している壺に手をやる。素焼きの壺は内側に銅が貼られている。気休め程度ではあるものの、中の湯はまだ温かい。自由の民から授けられた知恵だ。
採り溜めておいた薬草に手を伸ばし掛けたところで、がさがさと草を掻き分ける音がした。目をやると、寝惚けた目を擦る青年がぼんやり立っていた。
「すまない……寝過ぎてしまったようだ」
青年はもつれる舌をほどきながら何とか口を開く。ルシフェルは小首を傾げた。
「おや、もう少し寝ていても良かったんだが。おはよう、イーノック」
「おはよう、ルシフェル」
イーノックは手で隠そうともせず間の抜けた欠伸をした。目を開くと大天使が薬草をひと掴みしていたので、思わず表情を曇らせる。効力は起き抜けの身体の軽さで実証済みだが、あの青臭さは勘弁願いたいところだ。
青年はそそくさとルシフェルの隣へ腰を下ろし、壺に自らの武骨な手を重ねた。
「私がやるよ」
「休んでいて構わないぞ。今日は君の為の安息日だ」
「いや、大丈夫だ。こういうものは自分でやらなくては」
ならお願いしよう。大天使は疑いもせず壺を開け渡して、掴んでいた薬草を放り出した。手を払う。付着していた草がぱらぱらと落ちる。四方八方に舞ったそれらを掻き集めて、青年は間一髪命拾いをした。ふうと息をつく。
イーノックは集めた草達の中から、飲み慣れた種類のものだけを選び出す。大の男が指先でちょいちょいと一本ずつ薬草を分ける光景は少々滑稽だった。効能の高い草は概して苦味と渋みが強い。自分から進んで飲む気は起きなかった。擦り潰して丸薬にでもした方がいいだろうな。器に選り分けた後の薬草を千切り入れながら青年は思う。暇のあるときにでも煎じておけば良いだろう。
だが、彼がいけないのはその算段を口を閉じたまま行ったことだった。薬効の高い草ばかりを避け始めたイーノックを、ルシフェルは訝しく思った。赤い爪先を、つ、と向けて、男はけろりと尋ねる。
「それは入れなくていいのかい」
そう問い掛けた天使は無罪だ。イーノックは手を止める。これが入ると苦くて不味くなるから。たったそれだけを、彼は言い淀むような男だった。神が与えて下さった糧に対して、不味いなどと言って子どものような駄々を捏ねてはいけない。そうして自己完結してしまうような生真面目な男だった。しかし、舌は既に昨夜から渋みで痺れてしまっている。
愚直な男はからからと頭を回して、最もこの場に相応しい言い訳を考え出した。
「だいぶ調子が戻ってきたから。頭の中も、昨日よりは洗われたように感じるよ」
ぐにゃり、と。
ルシフェルはこんがらがったような表情をした。魚の小骨が喉を突いたような、癪(しゃく)が痛むような、そんな顔だ。イーノックもこれには何かを察知して思わず彼の鼻先を凝視した。
怒り、不安、悲しみ、憐れみ。濁流のごとく流れていく負の感情。
「ルシフェル――?」
大天使は大いなる右手で己の口元を覆い隠し、小さく言い放つ。
「そうか。それは良かった」
口調は冷たく突き放すようだった。ぞくり、とイーノックの背筋が毛羽立つ。昨晩の甘い囁きはどこへやら、それはエゼキエルの死を前にしたルシフェルと同じ姿だった。
自分の何が大天使の琴線に触れたのだろう。敬虔な男は途端に恐ろしくなって、燃え盛るような怒気を孕んでいる天使へ思わず平伏した。人智を超えたものを前にしたときの行動だった。
「何をしているんだ」
下げた頭に掛けられた声は思ったよりも悠然としていたが、イーノックは決して頭を上げなかった。美しく、愛しているはずのあの赤い瞳が、今は蛇のように思え恐ろしくてならなかった。
何故だろう、と自らの激しい動悸に身体を揺らしながら書記官は己を省みた。何故、この頃のルシフェルはこんなにも剣呑としているのだろう。罅(ひび)の入った硝子板のようじゃないか。いつ割れるとも分からない、いつ切っ先がこちらを向くとも分からない。
天界にいた頃のルシフェルは、こんな風ではなかったはずだ。最初こそつっけんどんな態度ではあったが、親睦を深めるにつれ笑顔を見せてくれるようになった。足繁くイーノックの書務室へ通っては、下界土産を山ほど抱えてくるような天使だった。愉快な男だった。イーノックはルシフェルが大好きだった。
それなのに、堕天使討伐の旅を始めてからというもの、自分達の歯車は確実にどこかでずれてしまった。それがただ辛く、哀しい。
すい、と手が伸びてきた。二本の手だ。白い手は撫でるようにイーノックの頬を包み、強制的に上を向かせる。見知らぬ男のような顔をして、ルシフェルが正面から青年を見据えていた。
「頭を上げるといい」
赤い瞳はやはり濁っていたが、唇が紡ぐ言葉の調子は綿のように優しかった。
「全く、君は何をしているのかな。私の顔を見られないようなことをした覚えでも?」
イーノックは目を伏せたまま、緩やかに首を横に振った。分からないんだよ、と言ってしまいたかった。分からないんだよ、ルシフェル。私が何をしたのか、あなたを何がそうさせているのか、私には何も分からないんだよ。全ての意味を含ませて、言葉の少ない彼は首を横に振り続ける。
「なら、そうして無意味に額を地面に擦りつけるのはやめてくれないか。
私も心苦しいし、そんな関係は欲しくない」
二本の腕は細かったが、驚くほど力強かった。ルシフェルは跪く男の肩をがっしりと掴むと、平伏したままの彼の身を否応なしに起こさせた。
額には砂利と泥がついている。大天使は手首で汚れをぐいと拭ってやった。泥は斜め上へ伸び、書記官の情けない顔に一筋の直線を描く。ハの字に眉を寄せるイーノックの顔を眺め、ルシフェルはようやく表情を和らげた。イーノックがあまりに弱々しく、人間らしく見えたからだ。
砂利を人差し指の爪で摘まみ上げると、前髪の生え際に祝福の口付けを落としてやる。
「すまないな。《背徳の塔》内の穢れの影響がまだ残っているようだ。必要以上に気が立っているのが自分でも分かるよ。肉を持たない私の身体に、あの穢れは強過ぎる。
さあとっとと薬湯を淹れて、それから顔を洗ってこい。顔に泥を塗りつけたまま朝食というのは、どうも文明人らしくないからね」
ルシフェルの表情がまた穏やかな毛布のようになったので、イーノックの心は今度こそ散り散りに乱れてしまった。天使の考えが欠片たりとも分からなかった。どうしてそうも気を立てているんだ。あなたの薫り立つような天使の微笑みは、どうすれば戻ってくれるんだ。
考えていると自分の気まで苛々と立ってくる気がしたので、口付けの痕を指で抑えながら、そうする、とイーノックは答えた。
安息日には休まなくてはならない。たとえ休みたくなくとも、休まねばならないのだ。休息を取るということが極端に苦手なイーノックにとって、安息日はどうしても手持無沙汰になりがちな日だった。
与えられた猶予が無限にある訳ではない。穢れが地に満ちれば洪水計画は実行される。一刻も早く堕天使を捕縛しなければ、地上の生命は皆押し流されてしまうだろう。気ばかり逸るのだが行動は起こせない。何度迎えたところで、やはりこの日だけは苦手だと書記官は魚を食みながら思った。塩焼きした魚は小骨が多く身も少ない。おまけに少しばかり塩が効き過ぎている。薬湯が美味いのだけが幸いだった。重ねていた枯れ葉の香りがどことなく染みついている。
イーノックが冷えた魚の身を咀嚼している間、ルシフェルは何をするということもない。物を口にする必要はないし、賛美の祈りを捧げる必要もない。
自由に時を行き来できる大天使にとって、何かを『待つ』というのは驚くほど難しい行為だった。その気になればいつでもパチンと指を鳴らしてしまえばいいのだ。それだけでルシフェルはどの時間地点にも降り立てる。青年の長い食事時間に辟易したなら、パチン。それだけで良いのだ。
しかしルシフェルはそうしなかった。今日も変わらずイーノックの傍にいて、彼の食事が終わるのを待っている。それがどれだけ素晴らしく、忍耐強いことなのか書記官には分かっていた。有り難い。心の底からそう思う。そして、まだ自分が友人と思われているだろうことを伺い知れるのだ。
焦げた魚の目はどろりと白く濁っている。命のない瞳だ。イーノックは躊躇わずそれにかぶりついて、小骨ごとがりがりと噛み砕く。鋭い骨が口内をあちこち突き刺したが構うことはなかった。何せ彼は腹が減っていたし、与えられた糧は綺麗に平らげるのが礼儀だと知っていたからだ。塩気が効いた皮と身を奥歯で擦り潰し、ぬるい薬湯でごくりと飲み下す。
天使は息もろくにせず、じっとそれを眺めていた。
全ての魚が胃に収まると、イーノックはゆっくり口を開いた。
「エゼキエル……の、魂は天へ昇っただろうか」
おそるおそる切り出された言葉にルシフェルは顔を上げた。黒い天蓋の向こう側の空に思いを馳せるようにして、すっと目を細める。見えない何かを見るようにして目を凝らした後、ほとんど独り言のように呟いた。
「ああ。ここからでも見えるよ。彼女の母性愛に満ちたアストラル体がね」
ルシフェルの言葉はイーノックの罪悪感を少し軽減させた。自分は役目を果たせたのだ。神のお役に立てたのだ……たったそれだけの僅かな誇りが今の書記官を支えていた。我が身に訪れた幾度とない死も、放った刃も、辛い選択も。全てがその誇りの為にあり、神の為にある。そう思い込むことにより、老婆のあの凄惨なる死も徐々に薄れていく気がした。イーノックは努めて言い聞かせることにした。
ルシフェルは淡々とした面構えをしている。友人を見る目付きではなく、たとえるならば、品定めをする視線だ。大天使はイーノックのアストラル体をぐるり見渡す。そして魂の回りに茨のように張り巡らされた、肉体とアストラル体を繋ぐエーテル体を見た。どちらも恐ろしいまでに澄んでいて清らかだ。しかし、あくまで人間の範疇での清らかさに過ぎない。
天使は薄く唇で弧を描いて、それから声を出した。
「何故彼は、君を選んだのだろうな」
それがあまりに老爺のように掠れた声だったので、イーノックは驚いて目の前の男を見た。
「ルシフェル?」
「何故この旅に君を選んだのだろう。君でなくても良かったはずだろう」
薬湯は遂に冷め切っている。
性急さを含んだ調子でルシフェルは続ける。自らが抱えた秘密を掠らぬよう、それでいて何かが伝わることを望みながら、まくし立てる。
「洪水? 起こすなら起こしてしまえば良かったんだ。君に相談などせずに。
君は人間なのだから、計画を知れば反対することなど端から分かっていたはずだろう。第一、地上全ての尻拭いを君にさせようとする方が間違っているんだ」
「ルシフェ、」
天使の手が青年の腕を掴んだ。爪が皮膚に食い込む。
「神は絶対だ。彼の力を持ってすれば、地上の穢れなど君の力無しで祓えるとは思えないか。君が旅をやめようと――世界はあるべき方向へ流れていくと、そうは思わないか。イーノック」
向けられた目は真剣で、渇望と庶幾に満ちていた。ルシフェルがこれほど泣きそうな顔を見せるのは初めてだったので、イーノックは戸惑った。
選択の自由を持たない天使にとって、言葉にできるのはそこまでだった。人間の青年に命令することも、彼の選択を覆すこともルシフェルにはできない。遠まわしな言葉で忠告するのが精いっぱいだった。
イーノックは自らに告げられた言葉の意味を懸命に考えたが、いい答えは浮かばなかった。ただひとつ言えることはある。
「……だが、旅はやめられない」
青年は一瞬の沈黙の後、そう宣言した。見つめ続けるルシフェルの前で、仄かな微笑みを浮かべながら、イーノックは困ったように息を吐いた。
「確かに私の力など微々たるものだ。この旅だってあなたのサポート無しには進めぬほど、私は脆弱で儚い存在でしかない。
しかし、神がそんな私の力を望むというのであれば、私はいくらでもこの両腕を、身体を、全てを差し出そうと思っている。
……旅立つ前にも、そう約束したじゃないか」
ルシフェルは押し黙った。黙ったまま、仕方なく青年の決意を聞いていた。
あまりに大天使が黙ったままでいるので、イーノックは段々と不安に思えてきた。また自分は何か間違ったことを言ったのだろうか。おろおろと見苦しくうろたえながら、イーノックはルシフェルの機嫌を伺うように瞳を覗き込む。
「すまない。私が弱いばかりに、あなたに無茶なサポートばかりさせて」
「君は強いよ」
赤い瞳は微かに濃い色をしていたが澄んだままだった。泣きそうな表情を取り下げて、天使は俯く。影の下では諦観に満ちた顔をしていた。
「君は強い。――弱いのは私の方かもしれない。
私は、君がした選択のサポートをするだけだ。それだけだ」
「ありがとう!」
その言葉に最上級の支えを得たように思えて、安堵したイーノックは無邪気な笑顔を浮かべた。積んだ枯れ葉の下では白く濁った目をした魚が数匹、夕餉の時刻が来るのを待っている。
→次へ
←前へ
▲戻る
|