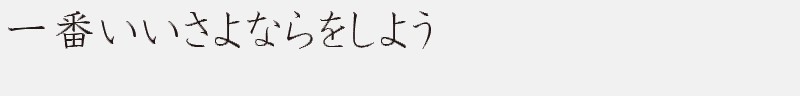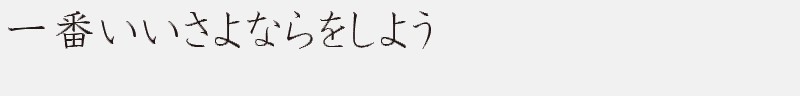|
02.ピリオドの先
イーノックは神の武器を握り直した。青白い刃が美しく煌めく。
最初に手にした武器はアーチだったが、最後に彼が手にしたのもまたアーチだった。因果なことだ。長い旅路にピリオドを打つべく、人間の書記官は武器を振りかぶった。そして刃は黒曜石で造られた塔の中央動力部へ。
振り下ろされたアーチはいとも容易く動力部を破壊した。黒曜石の欠片が飛び散る。散った破片は穢れと共に霧散し、後には何も残らなかった。
<背徳の塔>は全ての活動を停止した。実に呆気ない最期だった。長年タワーを守ってきたいくつもの目は安らかに閉じられ、堕天使へ魅入られた人々の魂と共に永遠の眠りへと就いた。塔は今や残骸と化した。瓦礫の山こそが堕天使たちが地上に残すことのできた全てだった。
イーノックは深く息を吐いた。肺を裏返してしまうかのような、感傷に満ちた溜め息だった。
終わったのだろうか。永久に続くとも想われた旅も、遂に結末を迎えることができたのだろうか。現実感はまるで感じられない。他人事のような顔を引っ下げながら、イーノックはその場にぼうっと立ち尽くしている。
パン、パン、と乾いた音がした。
振り返ればルシフェルが笑顔と共に手を叩いていた。
「やあ、お疲れ様。これで君に課せられた仕事は全て終わりだ。君の名前はあらゆる者から讃えられ、後世にまで語り継がれることだろうな」
何が可笑しいのか、大天使はくくと笑っている。
「そして、私もようやく天界へ戻ることができる。
君との旅は悪くなかったが、やはり長かったよ。これだけ何かをじっと待ったのは初めてだ。まあ、そういった意味では貴重な経験をさせてもらったよ」
ルシフェルは相変わらず饒舌だ。ぺらぺらとよく喋る。寡黙な男は天使の滑らかに動く赤い舌を見つめていた。その視線に天使は気付かない。
熱に浮かされたような瞳で、イーノックは彼をじっと眺めた。
旅の最中はこの天使の美しさだけが支えだった。闇の深淵へ心が沈みそうなときも、ルシフェルの存在がいつも彼を導いてくれた。孤独の淵にいるときも、悲しみの中にあるときも、だ。
喉に熱の塊が詰まる。終わったのだ。全て、終わったのだ。
喩えようのない煮詰まった気持ちがイーノックの中をぐるぐると渦巻く。四百年近い旅の想いを端的に表すことができるほど、彼は人間から遠ざかってはいなかった。イーノックはくしゃりと顔を歪めた。感傷が胸に迫り、いっそ苦しいほどだった。
書記官の苦しげな様子に天使はようやく気付いた。美しい大天使は笑うのをやめ、不可解そうに眉を下げる。
そして、言い放った。
「どうしたイーノック。まるで百面相だ」
歯に衣着せぬ物言いに、青年は愕然とした。ルシフェルは尚も不可思議そうにイーノックを覗き込んでいる。
「ようやく旅が終わるんだぞ。嬉しくないのか?
なんだ、そんな痛ましい顔をして」
――ルシフェルには分からないのだ。イーノックは確信した。
ルシフェルは姿形こそ人間を模してはいるが、人間とは全く違う生き物だ。ヒトが蟻の気持ちを理解できないのと同じように、天使がヒトの気持ちになることなど不可能なのだ。
彼とて分かってはいたはずだが、これほどまでに種族の境界線を突きつけられたのは初めてだった。
大天使は笑わないイーノックを興味深そうに観察している。真っ直ぐに通った鼻筋は白く、どこか人形じみている。
「嬉しい、とも」
イーノックは言葉を搾り出した。声は掠れている。
乾いた舌は上顎に貼りついていたので、剥がすときに不快な思いをした。
「うれしいからこそ、どんな顔をすればいいのか分からないんだ」
「ふうん。そんなものか」
突き放したようにルシフェルが言う。顎に手を当て、さも考えているような素振りを取っている。だが本当は何も分かってはいないのだろう。その推測が酷く青年の胸を痛めた。
考えることに飽きたのだろう。まあいい、とルシフェルは肩をすくめた。
「さ、天界へ帰るぞ。皆が君の帰りを待っている。役目が終わったのなら、ここにこうしている必要もないだろう?」
イーノックはぐるりと周囲を見渡した。
慣れ親しんだ景色。ようやく澄んできた風の匂い。ほのかの立ちのぼる土の香り。
地上にまつわるあらゆるものが書記官の五感を刺激した。甘い郷愁の念が胸を締めつける。これでもう、生まれ育った地を踏むのも最後になるのか。
ルシフェルを見やる。彼はせわしなく指先を擦り合わせている。
恐らく今感じているこの気持ちも、天使である彼とは共有できないものなのだろう。頑丈な壁で互いが隔たれている気がして、イーノックはとても哀しかった。
「ああ」
簡潔に答える。
書記官の思いなど微塵も知らず、ルシフェルは天使然とした微笑みを浮かべた。
「じゃあ、行こうか」
「……ルシフェル」
指を鳴らそうとした瞬間、イーノックがぽつりと呟く。出鼻を挫かれた大天使はきょとんと瞬きをした。
青年は沈み込むように俯いている。
「どうした。まだ何かやり残したことでも?」
「……てくれないか」
「うん?」
ルシフェルはのらりくらりと聞き返す。
「褒めてくれないか、私を」
苦しげに青年が漏らす。空っぽになったタワーの内部に彼の声が苦々しく反響した。
天使は首を傾げた。相変わらず人間はよく分からないことを言う、と呆れているようにも見えた。
だが彼は生まれつきの天使である。即ち長い睫毛を伏せると、低く落ち着き払った声でこう囁いてやる。
「『おめでとう、イーノック。よくやったな』」
「……ありがとう」
辛そうな表情を覆うようにして、イーノックはなんとか微笑んでみせた。泣き笑いに似た顔だった。
ルシフェルは書記官のそんな表情を認めると、さも満足気に鼻を鳴らす。この男の願いを完璧に叶えてやったと自負したのだ。
「戻るぞ」
青年は頷いた。砂でざらついた金の髪が小さく揺れる。
イーノックの胸はじくじくと膿を吐き出していた。
なんと馬鹿げたことを頼んでしまったのだろう。天使から投げ掛けられた言葉は哀しみだけを残し、彼の心をむごたらしく切り刻んだ。
あの言葉の中には、天使の義務としての響きしか込められてはいなかった。ルシフェル自身がイーノックへ贈る気持ちなど欠片も存在しえなかったのだ。それが旅の全てだった。
せめて同情だけでもあれば良かった。
四百年の旅を締めくくるべく、青年はすうと瞼を閉じた。
ルシフェルを責める気は微塵もない。彼と私は違うのだから、仕方のないことなのだ。ただただ今は辛く哀しかった。
指が鳴らされる寸前、閉じた目の端から一筋の涙が零れ落ちる。
その雫が地を濡らすより早く、独りと一匹の姿はかき消えてしまった。二人が消えた後には何も残されてはいない。
イーノックはルシフェルへ恋焦がれていた。
そして、それが叶うはずのない想いであることもよく分かっていた。
一羽の白鳥が天界へと舞い降りた。白鳥は虹色にその身を輝かせながら、ふわりと重力もなく着地する。エデンに住まう草木がそよ風にさわさわと音を立てた。彼らの来訪を歓迎しているようだった。
神聖な鳥は赤い目を向け、翼へ空気を含ませるとふかふかと気持良さそうに膨らんだ。
彼は己の長い首をうんと伸ばした。毛並みのいい首筋が光を受けて艶やかに動く。思うがままに伸びをして、白鳥はうっとりと目を細めた。
やがて、白鳥はぱちりと瞼を開く。ルビー色の虹彩は賢明な光を宿している。
突然、つむじ風がその場に舞い上がった。木の葉や砂埃が勢い良く渦を巻く。白鳥は荒れ狂う渦の中であっという間に黒い靄のようなものへと変化して、激しい流れへと溶け込んでしまった。
そして次の瞬間にはもう靄さえもが霧散してしまっている。つむじ風は止み、再び木の葉たちはぱさりと地面に投げ出された。
渦のあった中心部にはルシフェルがゆらりと立っている。
彼は赤い目を静かに瞬いた。何事もなかったかのような顔をして、大天使は服の裾を手で払う。
「ふう」
歩き出しながら息をついた。
天界は常春だ。ルシフェルはまんじりともせずシャツの首元を緩めた。久々の清らかな大気を感じる。ようやく肩の荷が下りた気がして天使は首を回した。
ぱちん、と軽快に指を鳴らす。再び黒い靄が出現し、その中から今度はイーノックが現れた。
書記官はよろめきながらもなんとか地面を踏み締める。
顔を上げると、前方にルシフェルが歩いているのが見えた。黒いシースルーのシャツを羽織った天使は振り向きもせず、足を投げ出すようにしてぼちぼちと歩いている。
見慣れた仕草にほっと安堵する。飼い犬の如き従順さでイーノックは天使の隣へ駆け寄ろうとした。
「ルシフェ……」
だが残酷にもそこに、ピリリリ、と着信音が鳴り響く。
青年は思わず足を止めた。
黒髪の天使は途端に嬉しそうに顔をほころばせ、尻ポケットへと手を伸ばす。
温和な表情は決してイーノックには向けられたことのないものだった。
ルシフェルはいそいそと携帯を取り出している。慣れた様子で手の中に携帯を滑り込ませ、柔らかな微笑みと共に右耳へと押し当てた。書記官はそんな彼の様子を、まるで映画のスクリーンでも観るようにぼんやりと眺めている。
「やあ。ただいま、と言うべきかな。うん、終わったよ。今からそっちに顔を出すから……うん。ははは! あまりこき使ってくれるな。私だって疲れてるんだ。
……うん? ああ、あいつか」
そこで初めて天使は青年の方を振り向いた。突然の視線にぎくりと身が跳ねる。
注がれているのは品定めをするような眼つきだ。紅色の瞳が炎のように揺らめいている。
「心配しなくともちゃんと連れ帰ってあるよ。サポートくらいきっちりやるさ。
え、君の部屋に? おいおい。随分と唐突な話だな。聞いてないぞ。
……いいや。君の頼みなら是も否もないさ。分かったよ、ならまた後で」
不服そうな声色を隠そうともせずにルシフェルは応えた。
用件が済むと通話を切る。切ってからも彼は暫くの間、ブラックアウトした液晶画面をじっと見つめていた。
天使の微笑みとはまさにあのことを言うのだろう。イーノックは熱っぽい溜め息を吐いた。
だがどれほど焦がれて見つめたところで、彼がこちらを顧みることはない。
「喜べイーノック。彼が君に会いたいそうだ」
実に晴れやかな面持ちでルシフェルが言う。
「神が人間の前に姿を現すことなんて滅多にないんだ。よほど君の功績を喜んでいるらしいな。誇っていいぞ」
「ああ」
「なんだ、つれない奴だな」
つれないのはあなたの方だ、という台詞が喉元まで出かかった。ぐっと飲み込む。嫌な味がした。
ともあれ、敬愛する主に直々に御目通りできる機会を得たことはイーノックにとっても願ってもないことだった。旅立つ前、天界の書記官を務めていた身の上でも挨拶すら叶わなかったのだ。
神が会うのは上級の大天使のみだよ。
そう聞かされながらイーノックは、何度神の記した文字を指でなぞったことか。
天界のモノクルを使ってでしか読めぬ、この美しい文字。一体どんな方がどのようにして綴ったのだろう。昔は仕事に精を出しながらそんなことばかり考えていたものだ。
ふむ、とルシフェルが唇を尖らせる。
「しかし珍しいな。もしかすると……」
意味深な天使の呟きに書記官は首を傾げる。
「彼は君を天使にするつもりなのかもしれないな」
興味深そうに放たれた言葉に、イーノックは驚嘆して目を見開いた。
「私が、天使に?」
「そう大袈裟に声をあげるな。単なる憶測だよ。
ただ君はこれから未来永劫にいたるまで、悠久の時をここで暮らすんだろう? それなら無理に人間の器でいるより、我々のような存在でいた方が効率的じゃないかと思ってね」
「天使……」
書記官は押し黙ってしまった。夢うつつにたゆたっている気がしてならなかった。
目の前に立つ大天使は荘厳で偉大に見える。
彼らと同じ種族の生き物に、私もなれるというのだろうか。より近く神のお傍へはべり、人間であるときより強大な力を主の為に揮えるというのだろうか。
旅立つ前のイーノックであれば、盲目的にこれを受け入れられただろう。喜んで肉でできた己の身体を捨て、献身的に我らが主へ仕えることができただろう。
だが、今のイーノックはどうだ。口を一文字につぐんだまま沈黙を保っている。胸中は複雑な想いで淀んでいた。あらゆる感情がいくつも絡み合い、彼の中で深く根を張る。まさに混沌と呼ぶに相応しい有様だった。
イーノックは青い目でルシフェルをじっと見つめた。
陶器のように白い肌、カラスの濡羽色をした睫毛。そしてひときわ目を惹くのは、蜃気楼のように色を変えるルビーの瞳。
心臓が高鳴る。
もっと見ていたい。もっと彼に見られていたい。
この清らかで美しい彼の存在を愛でる気持ちも、天使となったときには失われてしまうのだろうか。恋慕などという浅ましい想いは淘汰されるべきものなのだろうか。
書記官はぎゅっと胸を押さえた。爪の跡が剥き出しの胸板へと刻まれる。
ルシフェルは眉根を寄せた。イーノックの元へ浮き草のように歩み寄ると、目の前で大袈裟に手を振ってやる。
「おい、フリーズするな」
青年は自分を覗き込んでくる目に、はたと気付いた。鼻と鼻の先が今にも触れ合いそうな近さだ。
あまりの近さに純朴な男は思わず身を引いてしまう。
「すまない。大丈夫だ」
「まったく。今日の君は一段と呆けているぞ。使命が終わったからとはいえ気が抜け過ぎなんじゃないか」
随分と辛辣な物言いだ。イーノックは困ったように唇を歪ませる。
「人間は容量が少ないから、すぐ考え込んでしまうんだよ」
「なら、やはり君は天使になるべきだな」
はは、と青年は心のない笑いを吐いた。
足を踏みかえ重心を変える。身体は重い。
「主の元へ行くのだろう」
「おっと、そうだった。こんなことをしている場合じゃなかったな」
大天使は厳かに言い、イーノックの腕をおもむろに掴んだ。褐色の肌はルシフェルに掴まれた部分のみ白く浮かび上がる。
「ここからなら翔んだ方が早い。掴まっていろ」
イーノックは掴まれた自らの腕を見やり、凛々しい大天使の顔を見た。神の元へと逸る紅潮が表れている。
自然と青年は捨て犬のような表情になってしまった。眉尻を苦しそうに下げ、口角だけは吊り上げる。
「あなたは本当に彼が好きなんだな」
「好き、とは少し違うよ。そんな陳腐なものじゃない」
整った天使の横顔を見ながら、イーノックは腕を握り返す。
強く強く、決して置いて行かれぬように。
「陳腐、か」
「翔ぶぞ」
ルシフェルが地面を蹴る。六対の翼が一息に広げられ、二人の体は宙へと浮かび上がった。
大天使に導かれるようにしてイーノックは宙を舞う。天使が羽ばたくたびに太陽の匂いがした。
彼の翼の香りだろうか。
己の気持ちを持て余しながら、イーノックは静かに息をしている。
→次へ
▲戻る
|